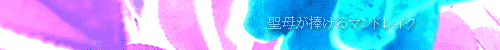
嵐の前の夜は静寂に包まれるという。
ほら、貴方の傍に静かな夜が忍び寄ってきた。
その日、瀞霊廷に雷が落ちた。
雷は禍の象徴。
激しい雨が降っていた。
「ルキアッ!!」
突きつけられた刃物が、首を傷つける。
そんなことは構わない。
喉を裂く刃の感触と、したたる血を感じながら、それでも一護は叫んだ。
捕らわれた少女に向かって。
「黒崎副隊長」
首に刃物を突きつける砕蜂の声は、刃物そのものだ。
「…我らに刃を向ければ、そなたを反逆人と見なす」
夜一の声は、確かに一護の耳に届いたけれど。
一護は斬魄刀を開放しようとした。
「一護」
斬月を握る、その手を掴まれた。
その力で、一護の霊力をねじ伏せる。
そんなことが出来るのは、自分の仕える隊長以外、いないではないか。
薄れていく意識の視界で、ルキアを捉えた。
ルキアは一度も振り返らない。
*
その日、五番隊隊長藍染惣右介の死体が見つかった。
致命傷は心臓の一突き。
けれどその身体は刀傷でいっぱいで、怨恨深い犯行だろう、と刑軍の一人が言った。
穏和で人望厚く、誰にでも慕われていた藍染を、そこまで恨んでいたのは誰だろう。
残酷に凄惨に殺すほどに至らせたものは何だったのだろう。
目の前の少女は真っ青だ。
いつの間にか合わなくなった視線を向けて、一護はその告白を聞いた。
ルキアはこんなに小さかっただろうか。
「私が、… 私がッ」
「ルキア?」
ついに震えだしたルキアを、一護は抱き締めた。
ちょうど同じ高さのその頭のてっぺんを見つめた。
「、藍染、隊長を…ッ 藍染惣右介を殺したのだっ」
藍染が殺されたという知らせは、護廷内を駆けめぐった。
当たり前だ。
一個隊の隊長であるとともに人格者だったのだから。
「じょう、だんだろ?」
冗談などではなかった。
ルキアの手には、切っ先が藍染の身体の中に割り入る感触が、臓腑を切り裂く感触が残っていたのだから。
「藍染殿に恨みなどないっ!けれど、私は藍染隊長を殺してしまった!」
私の中に、私以外の誰かがいるのかもしれない。
一護の中には、一護以外の男がいるように、ルキアの中にもいるのだろうか。
「ッ 」
一護はルキアの手を取った。
走り出す。
「一護!? どこへ行くのだ!」
今犯人を血眼になって探しているだろう、刑軍のところか。
それともルキアの兄の所か。
「俺は、お前が殺したなんて思っていない。でも、お前はそう思ってるだろ。だから、逃げるんだ」
「どこへ!」
「現世に決まってるだろッ!」
ルキアのことだ、この後きっと自首しに行くだろう。
けれど兄とは別の、最も近しい友に、懺悔したかった。だからその前に一護の元へ来た。
ルキアは殺してなんかいない、人を殺せるような人間じゃない。
副隊長である男を、成り行きとはいえ殺してあれほど嘆き悔いる少女が人なんて殺せるわけがない。
一護は地獄蝶を管理している部屋に向かった。
現世に行くには地獄蝶が必要だ。地獄蝶を捕らえた部屋の鍵は一護が持っている。
「ならぬっ!一護を巻き込むわけにはいかん!」
「うるせえっ。俺がそうしたいんだ。巻き込まれた云々じゃねえよっ」
地獄蝶を管理する塔に辿り着いた。
ここには十二番隊の隊員分の地獄蝶が飼育されている。
その襖に手を掛け、鍵を差し込む。
回して、襖を開く。
「… 現世に行って、どうするんです?」
開くはずの扉が開かない。
押さえつけられているからだ。
底冷えするような声が届いて、一護は慌てて振り返った。
「虚が、出たんだ。救援が、あって」
「今は第一級警戒態勢でしょう?副隊長であるアナタが招集されるはずがない」
そうだ。
藍染が殺されたとわかって、総隊長は第一級警戒態勢を引いた。
だから一護は、初めて「あざみ」を刻む副官章をつけた。
「もう一度聞きます。アナタは朽木ルキアと何をしに現世へ行くんです?」
一護はそんな目で見られたことなど一度もない。
見るもの全てを凍えさせ、い殺すような目。
「十三番隊所属朽木ルキア。藍染惣右介殺害の嫌疑で連行する」
夜一が立っていた。脇に砕蜂を従えて。
「ルキアッ!」
必死につないでいた手が離れてしまった。
*
「一護の首の傷はどうじゃ」
「たいしたことはありません」
幼なじみの声に、浦原は振り向かない。
その視界に映るのは、首に包帯を巻き横たわる一護だけ。
「そんなに怒るな、喜助。砕蜂とて、したくてしたわけではない」
「別に怒ってませんよ」
「だったらなぜ、そのように眉間に皺を寄せる」
幼なじみには浦原がどんな表情をしているかなんて筒抜けだ。
そういう彼女だって泣きそうな顔をしている。
「もしアタシが誰かを殺したなら、一護さんはアタシの手を取って、どこか遠くへ逃げようって言ってくれるのかな」
一介の隊員が隊長を殺す。それは第一級の犯罪だ。
その犯罪者を連れて現世に逃げるのは、それだけで罪に問われる。
良くて永久追放。
悪くて死刑。
一護はそれだけのことをしようとした。
知らぬはずがない。
その覚悟があったのだ。
「おぬしはこの件をどう思う?」
浦原は視線をようやく一護から外した。
振り返り、扉に寄りかかる夜一を見た。
「藍染に手を掛けたのは間違いないでしょう。そして藍染も間違いなく死んでいる」
「誰かに操られていた、という可能性は?」
「彼女には殺した記憶もある。薬ではそうはいかない。幻術もありえません」
第一、目撃者が居る。
朽木ルキアが、藍染惣右介を切り刻んでいた、と。
だからすぐに藍染は死んですぐに見つかったのだし、ルキアも捕らわれた。
早い時点で犯人がわかったからこそ、一護の逃亡幇助という罪が確定せずに済んだのだ。
「アタシには関係がない話です。大体、刑軍の大将がこんなところで油を売って良いんですか?」
おぬしはつくづく自分以外はどうでも良い男よの。
そう吐き捨てて舌打ちした夜一は消えた。
彼女も事後処理で忙しいのだ。
何せ犯人は平の隊員と言えども四大貴族の一つ朽木家の娘なのだから。
「昔は確かにそうでしたよ。でも…今は違うんです」
誰もいなくなった部屋で、誰もいないそこに向かって呟く。
そう、自分以外はどうでも良かった浦原に、世界に色があることを教えたのは一護だ。
人に対して愛おしいと、狂おしいという感情を覚え、そして同じように愛を返してくれた。
だから助けた。
現世に逃げる一護を止めた。
夜一に斬りかかろうとする一護を止めた。
「…朽木ルキアに、近づけるんじゃなかった…っ」
一護はルキアを友と呼ぶ。ルキアもまた一護を友と呼んだ。
おそらく無二の友だと思っているのだろう。
その優先順位はどちらだろうか。
浦原は一護無しでは生きてはいけない。
彼にとって、一護は無二の存在だ。一護にとって浦原はどうだろう?
「ねえ一護さん。どうかアタシの手を取って逃げてくれると誓ってください」
今は眠る一護に神聖な口づけ。
一護は目覚めと共に、二週間後、ルキアが双極に貫かれることを知るのだ。