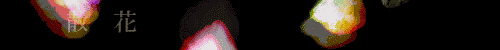
桃の花びらが散る。
如月。
暦の上では春であっても、突き刺すような寒さだ。
一護は顔を上げた。
目尻には薄紅色の花弁。
声は出ない。
出るはずの嗚咽は、雪と共に飲み込まれ。
覚悟はしていた、なんて口では言っても。
「……ッ」
雪がしんしんと降る。
ぽろぽろと零れる雫が、凍えるような寒さに凍り付いて。
真珠のように落ちていくのではないか、と。
*
あいつ、変わったよな。
そのたぐいの言葉は、基本として良くない意味で使われる。
恋次はそう言った。
より一層仕事に打ち込むようになった友人へ。
「一護」
「何だ?」
雰囲気も変わった。
目つきは元々悪くて、口だって悪い。
けれどこんな、触れたら傷つきそうな、凍てつく氷の刃のような。
「今日の分は終わりだとよ」
「…わかった」
納得していなさそうな顔で。
第一、一護は昨日虚の討伐に出かけていて、今日の職務はその報告書の提出だったはずだ。
なのに、普段と変わらぬ仕事をしている。
「…その……あまり、無茶すんなよ」
恋次に言える台詞はそれだけ。
ん…、と。
今までのような甘えるような声はなく。
「分かった」
堅い堅い返事。
「…… 分かってねえじゃん」
この言葉を紡いだのは何度目か知らぬ。
一護の背中を見送って、恋次は息を吐いた。
一護の背中はあんなに小さかっただろうか?
*
あの橙の灯火を見たのは、昨年の春。
桜の花びらが舞う中、それに負けぬ色彩を放っていた。
護廷に入隊したばかりだというその子供は、早くも席官に上り詰め。
その霊圧の高さとそれに引けを取らぬ実力故に、上官から目を掛けられているという。
「…… あの子は?」
「ああ。一護ちゃんだね。浮竹のお気に入りだよ」
京楽は、傘を目深に被って。
目を細めて、その子供を見やった。
「浮竹が自慢してくるんだ。まるで娘が出来た気分なんだろうね」
おかげでボクは、可愛い花を毒牙にかける虫扱いだ。
おかしそうに笑う。
京楽自身、あの少女とは親しいとは言えずとも顔見知りの関係らしい。
「今年の夏、結婚するんだって。ほら、あの隣にいる子だよ」
鮮やかな橙に比べて、彩度の低い。
茶髪の男は、浮竹に頬を引っ張られる子供を笑って見ている。
「へえ…」
「人妻には手出さないってのに、浮竹の奴酷いんだから」
それはどうだか。
浦原は白い目を京楽に向けた。
酷い!浦原くんまでそう言うんだ?!と声を荒げていた。
その声に気づいて。
少女はこちらを向いた。
琥珀色。
蜂蜜色。
「一護ちゃーん!」
頭を下げてくる。
騒いでいるのが京楽だと分かったのだ。
それに隣にいる隊長羽織を纏った男…つまりは自分、浦原に対しても。
浮竹が、何かを言っている。
おそらく、京楽なんかに挨拶をしなくて良いと言っているのだろう。
浦原は男を見た。
人並以上には整った。
優しそうな顔をした男。
数ヶ月後には、一護の夫になると言う男を。
浦原は口元に、笑みをたたえた。
*
死神の魂は、尸魂界で死ぬとまた現世に帰る。
けれど一護の夫であった男の魂は、二度と帰らない。
虚に食われてしまったから。
瀞霊廷が見下ろせる小高い丘。
死した死神が眠る丘。
その大地に魂はない。
その代わり、墓標の下には義骸が眠る。
永遠に腐らぬ特殊な義骸。
「… −−」
男の名を。
この大地に義骸を埋める男を、認識するその言葉を。
刻まれた石に一護は指を沿わせて、呟いた。
傍には行けない。
行きたいのに、行けない。
だってその魂魄は、この世界の何処にも存在しないから。
「…バカ野郎…っ」
この地へ立って何度罵ったことか。
優しい男は、決して弱くはなかったはずだ。
一人にしないと、言った男は。
一護をこの世界で独りぼっちにさせた。
「…泣いてるの?」
男の声音に、似ていると思った。
その優しい口調も。
一護は振り返る。
そしてやはり『似ている』だけであったと落胆した。
「…… 浦原、隊長…?」
そこにいたのは、十二番隊の…?
色彩も違う。
枯草色も、くすんだ翡翠も。
彼の人は持ち合わせていない。
言葉を交わしたこともない男は、細い指先で一護の目尻をなぞる。
「忘れられないの?」
忘れたい。これ以上傷つきたくない。
忘れて良いよ、幸せになって欲しいと男は言った。
ただ時には思い出して欲しいと言った。
忘れられる、はずがない。
ふれあった温かさも。
つながりあった熱さも。
「そう」
どうして、そんなことを聞くのか。
気に病むな、と皆告げて。
どうして病まずにいられようか。
男が虚に食われたのと同じ。
一護のココロも食われてしまった。
「……忘れさせてあげる」
深い闇を宿す。
その瞳は虚にも似て。
ああ、食われるのだ。
*
あの子、変わったわね。
半年前、伴侶を亡くした少女は、いつしかよく笑うようになった。
花のように。
「浦原さん」
くすくすと笑みを零す。
薔薇のように綻んで。
虚ろではない。
この感情は、あの子供本来のもの。
辛く悲しい記憶を失ったのだ、と誰かが言った。
「どういうことだい?」
京楽は酷く冷えた声で。
一護は不思議そうに首をかしげた。
浦原と絡めた指先はそのまま。
「この子が、望んだんすよ」
アタシは、その方法を知っていただけだ。
「そんなことをして、虚しくないのかい?」
「この感情は、本物だ」
浦原を愛するようになった気持ちは。
ただ、愛する人を失ったという記憶がないだけ。
嘘偽りはない。
「…… ずっと、欲しかった。いなくなってくれたのは好都合でしたよ」
でなきゃ、殺していたかも知れない。
口外にそう告げて。
浦原は絡めた指先に、口づけした。