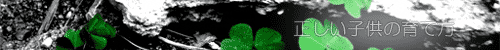
バタバタ、と忙しい足音に。
バーン、なんて五月蠅い音を立てて。
「っ一護さん!」
「儂が先じゃっ」
隊首室に入ってきたのは、枯草色の少年と褐色の少女。
「聞いてく「あので「お前ら、そこに直れ」
我先にと互いの言葉を遮る少年少女の言葉を、一護はさらに遮った。
「毎回毎回!襖は丁寧に開けろって言ってるだろッ この餓鬼共が!!」
一護が見やるのは、彼らではなく、既に残骸と化した襖だ。
白い肌に浮かぶ青筋は、きっと見間違えではないはず。
怒鳴り声に身をすくめてた彼らは、ごめんなさい、と声を揃えて謝った。
逆らってはいけない。
けれどそれでめげる彼らではない。
「いっそ殺気石で作ってみたらどうでしょ?だったらなかなか壊れませんよん」
「名案じゃ!喜助のくせになかなか良いことを言うではないか」
「てめえらが壊さなきゃ良い話だ!」
一護は、喜助と呼ばれた少年の頬を掴み、左右に引っ張る。
いらいれすよう(痛いですよう)と喜助は告げた。
「夜一さんも。女の子なんだから、ちっとはお淑やかになれよ」
「一護さんには言われたくない台詞ですねえ」
より、左右を掴んだ手を引っ張った。
夜一がそれを恨めしそうに見ている。
「で、何を言いにきたんだ?」
案外柔らかい頬を何度も伸ばしたりして、一護は夜一に問うた。
アタシは?という喜助の声は無視。
夜一は嬉しそうに笑って、喜助を蹴って押しのけると一護にしがみついている。
「刑軍に入ることが決まったのじゃ!学院も飛び級で卒業できることになった!」
夜一は四楓院家の次期当主で、刑軍に入ることは生まれたときから決まっている。
けれど実力がなければ、霊術院に入ることもましてや飛び級で卒業なんてあり得ない。
四回生だったはずだから、二回の飛び級だ。
「おめでとう。さすがは夜一さんだな」
若干背の低い夜一の頭を、よしよしと撫でる。
ごろごろ、と声が着きそうなくらい気持ちよさそうにしている。
鬼道の才があるし、そのうち猫になるんじゃないのか。
「褒美は貰えぬのか?」
夜一は目を輝かせている。
何でも買って与えられるお姫様が、褒美をと欲しがるのは、慕っている一護から何かを貰いたいのだろう。
それを重々分かっていた一護は、逡巡して、自分の首元に手をやった。
「これ、お古だけど。あ、新品の方が良いか?」
「それが欲しい!」
その声に一護は、いつも付けているチョーカーを外した。
そして夜一の首に付けてやる。
「良く似合うな」
「ずるいっ!」
夜一は褒め言葉に頬を染める。
蹴られてそこら辺に伸びていた喜助は、急に起き上がると夜一の髪を引っ張った。
痛い、と夜一が喚く。
子供だ。
「お前なあ…。女の子は大事に扱えって教えなかったか?」
喜助の手から髪が自由になると、夜一はいっそう一護にしがみついてきた。
それに喜助の顔が歪む。
「喜助。お前は?」
苦笑して、喜助を見やる。
拾ったときは胸の高さしか無かった子供はもう、一護よりも目線が高い。
「…一護さんの隊に配属が決まったんです。アタシも、今年卒業なんですよ」
手招きをして、喜助をこちらに呼ぶ。
脇に寄った彼の頭を、一護は手を伸ばして撫でてやった。
「良く頑張ったな」
背が幾ら成長しようともやはり子供。
零れんばかりの笑顔だ。
第一中身は子供のままだし。
「ご褒美はそうですね。一護さんが良いな」
「ったく…これで良いだろ」
喜助の頬に唇を寄せる。
幾分か高いところにあるから、背伸びして。
頬を染める喜助に、教育間違ったかな、と一護は後悔した。
「唇が良かったなあ」
「図々しい奴じゃ!去ね!」
このやり取りが気に食わなかったらしい夜一は、仕返しとばかりに喜助の髪を引っ張る。
痛い痛いというのは今度は喜助の番。
てっきりこの幼馴染みはくっつくものとばかり思っていたのに。
一護を巡って、好敵手の間柄になってしまっている。
ぎゃあぎゃあと喚き始める二人に、今日は仕事進みそうにない、と内心副官に謝ってため息をついた。
*
一護がお世辞にも綺麗とは言えない、小汚い少年を拾ったのは今から30年も前の話だ。
襤褸を纏って、流魂街に落ちていた。
流魂街に生きる人は、住む地区によって貧困の差がある。
現世よりも住みやすい良きところと言われて魂葬されるから、詐欺罪で訴えられたら終わりだな、なんて場違いなことを考えた。
「おい、お前。大丈夫か?」
治安も悪い貧しい地区で。
枯草色の髪をした少年が倒れていた。
それは、そう珍しいことではない。
時には死体となっていることもある。
仕事の息抜きとして、気まぐれに彷徨く流魂街。
その子供を拾ったのは、やっぱり気まぐれだ。
声に反応して、小さく身じろぎした少年を、一護は仰向けにさせた。
汚い身なりだが外傷はないようだ。
口元に耳を近づける。
やはり息はしている。
ぐう、と大きな音。
一護は合点がいって懐から水筒を取り出した。
少年の上半身を起こしてやって、口元に寄せる。
「水だ。飲め」
喉が動く。
少年の意識はないようだが、あっという間に水筒は空になった。
普通の魂魄は、腹など減らない。
だがこの餓死しそうな子供は、曲がりなりにも霊力があるということか?
一護は手を額に添えて、霊力を集中させた。
苦手だが全く使えないというわけではない。
光が収束して、それから離散する。
ゆっくりと。
長目の睫毛に縁取られた瞼が開く。
枯草色に反して、こちらは新緑だった。
「!」
驚いた少年は、立ち上がる。
きっと距離を取りたかっただろうに、立ち眩みにすぐに倒れ込む。
一護はその腕をとって、支えてやった。
「別にお前をどうこうするつもりはねえよ」
不審そうな目。
番号も後半に近い此処では当たり前かも知れない。
「腹減ってるんだろ? これ食えよ」
空の胃にはどうか、と思うが一護は懐に入っていた菓子を手渡した。
疑わしいそうにそれを眺めて、けれど貪るようにそれを口にした。
「なかなか豪快だな。男はそうでなくちゃな」
「…… アナタは、誰?」
掠れた声で、少年は一護を見上げた。
「俺は黒崎一護だ。お前は?」
「…浦原、喜助です」
喜助か、良い名前だな。
そう言って一護は喜助の頭を撫でてやった。
「よし、喜助。背中に乗れ」
一護は膝を曲げて、喜助に背を向ける。
その前に一応、背に負ぶっていた斬月を下ろした。
「…は?」
その背中を見つめて、喜助は呆然としていた。
「何だ、来ねえのか?」
「…何処に行くんですか」
一護は膝を曲げたまま振り向く。
屈んでいるせいで、喜助の方が高い。
見下ろされる視線を感じて、一護は苦笑した。
利発な子供だ。
「瀞霊廷って言って、此処から随分遠くにあるが、此処よりも良いところだ」
「…瀞霊廷、って死神が居るっていう…」
「そうだ。ま、そこにいるのが全員死神って言うわけじゃないけど、俺は死神だな」
瀞霊廷の存在を知っているのか。
内心驚きながら、一護は喜助の腰に手をやった。
「俺と来ないか?」
もしかして此処に家族と呼ばれる集団を築いているかも知れないが。
ここで息倒れていたのを見ると、そうでもなさそうだ。
「俺は独り身だから、話し相手になってくると嬉しいんだけど」
喜助の手が、一護の頬に触れた。
痩せこけた手。
幾分も一護より小さい。
「…… 行きます」
そうか、と一護は頬を緩ませた。
喜助の、血色の悪い白い肌に血が巡る。
「よし。帰ったらたらふく食わせてやるからな」
小さな手が肩に回る。
随分軽い喜助の身体を負ぶって、一護は立ち上がる。
「一護さん」
何だ、と背中にいる喜助に問いかける。
一護さんか。呼び捨てにされたらどうしようかと思っていたが。
「宜しく、お願いします」
「おお」
そう言って眠りに落ちた喜助の身体をしっかりと抱えて。
一護は帰路へ向かった。
流魂街に倒れる子供に施しをすることは何度もあったけれど。
この子供を拾ったのは単なる気まぐれ。
そう言ったら喜助は傷つくだろうか。
ただその枯草色の髪が、一人屋敷から見上げた空に浮かぶ月のようで。
一護の寂しさを紛らわせてくれそうだ、と思ったのだ。