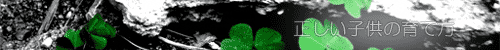
夜一ともう一人。
喜助には幼馴染みというか昔なじみが居る。
志波空鶴。
五大貴族志波家の長姫だ。
夜一といい肩書きだけは見事なものだと、喜助は思っている。
「よお弟」
女らしからぬ口調は空鶴の。
世の中のお姫様という想像からはかけ離れているのがこの幼馴染みだ(夜一もだが)
空鶴は死神ではないが、ちょくちょく喜助の居る十二番隊の隊舎に顔を出す。
弟?
あいにく、その場に空鶴の弟と呼べる人物はいない。
上の兄弟に比べてあまり造形の整っていない弟。
熱血漢で正直鬱陶しい彼だ、喜助が一緒にいるはずもない。
「お前のことだ、喜助」
居ませんよ、と鼻を鳴らす喜助を指さした。
人に指さすなんて、何て失礼な人。
「アタシはアナタの弟になった覚えはありませんよ」
一護に拾われた当初、同じ年頃だからと引き合わされて。
小間使いのように使われたことは覚えているが。
「何だ、一護から聞かされていねえのか」
ニヤニヤと笑う顔は厭らしい。
性格の悪さが滲み出ているようだ、と小さい頃手酷い目に遭わされた喜助は思う。
「兄貴が一護と結婚するんだってよ」
兄貴。
空鶴は長女だがその上に兄が一人いる。
志波海燕。
今は確か十三番隊、浮竹の元で副官をしていたか。
空鶴や夜一に馬鹿にされていた時代、彼女らを諫めていた良い兄貴分だったはずだ。
「一護が義姉になるのか。……なかなか良い」
空鶴のその言葉に、思考を止めていた喜助は目を見開いた。
夜一と同様、一護を慕っている空鶴はまんざらでも無さそうだ。
「ど、どういうことですっ?!」
「兄貴が一護と見合いしてな。順調な交際をしているらしい」
初耳だ。交際だ?
見合いしたことすら聞かされていない。
「お前が弟になるのは気に食わねえが、昔のようにこき使ってやる」
そんなものになって堪るものか。
第一、一護のことを母だなんて思ったことはない。
喜助は感情のまま、作業室から飛び出した。
走って走って。
バーン、と乱暴に隊首室の襖を開けた。
「お前!また壊したな!!」
罵声と共に、筆が飛んできた。
だが喜助はそれどころではない。
「志波さんと見合いしたって本当ですか?!」
筆を受け止めて、ずかずかと隊首室に進入する。
ぽかんとしているのは一護の副官兼自分の上司だ。
「海燕さんと?ああ、先月だったかな」
山本の爺さんに、そろそろ身を固めろと言われてよ、と一護は告げた。
副官を乱暴に押し除けた浦原は、一護の傍へ寄る。
「お付き合いしてるんですかっ?」
「おお。言ってなかったけ?」
寝耳に水だ。
水どころじゃない。
油が入ってきて、しかも引火したぐらいだ。
「ていうか、押しのけるなよ。お前の上司だぞ」
副官を無理矢理どけたことを咎められた。
そんなことどうでも良い。
彼を上司だなんて思ったことは一度もない。
一護の傍に仕えていて、何て憎らしい男だと思ったことは何度もあるが。
「アタシがいらなくなったんですか?」
「何でそうなるんだ」
まるで恋人同士の痴話げんかだ。
一護は頭を抱えている。
「一護さんは、独り身で寂しいからアタシを拾ったんでしょ! 結婚したら、アタシなんて必要ないじゃないですか!」
ああ、と一護は納得がいったように。
肩を掴んで、喜助は一護を揺さぶった。
気分が悪くなるから止めてくれ、と告げられ、その手を止めた。
「結婚したからって別にお前を蔑ろにはしねえって。そうだ、弟か妹が出来たら始めに抱かせてやるよ」
三席に相応しからぬ霊力を出して。
怒りも露わに、喜助は一護から手を離すと立ち上がった。
そうして喜助は紅姫を引き抜く。
「別れて下さい。今すぐ」
はあ、とため息をつかれた。
無性に腹が立って、紅姫を振った。
はらりと、橙の髪が落ちる。
「他の男との子供なんていりません。男もろとも殺してやりますよ」
今は、甘んじて三席にいるが。
霊圧で言えば海燕を凌ぐのだ、相打ちなんて惨めな真似にならずとも殺してみせる。
喜助の霊力が注がれて、紅姫が高く啼いた。
「喜助」
斬魄刀を解放させたことには流石の一護も眉をひそめて。
立ち上がると、幾分も高い背丈の彼を見上げた。
「もし結婚したら、一護さんを殺してアタシも死にます」
「無理心中は勘弁してくれ」
それでも一護の言葉は冗談めいている。
苛立たしい。
「ッ 一護さんなんて知りません!」
埒があかないから。
喜助は壊れた襖を思い切り斬りつけて、走り去った。
残ったのは無惨な姿の襖と。
「…隊長」
「悪い…早引きさせくれ」
不憫そうに副官に見つめられて、一護ははあとため息をついた。
*
天照大神が天岩戸に閉じこもってしまったように。
喜助は屋敷の自室に閉じこもっていた。
はあ、とその襖の前で一護は重々しいため息をついている。
扉はうんともすんとも言わない。
力で押さえ込んでいるわけではない。
喜助は鬼道に長けていたから、結界を張って開かなくしているのだ。
「喜助。いい加減機嫌直せって」
触れることさえ出来ない襖。
それだけ喜助は拒んでいた。
長時間立っている一護の足は棒になりそうだ。
「俺が結婚することの、何が気に食わないんだ?」
喜助の霊圧がより乱れる。
これは怒りに触れたな、と一護は思ったが、口に出した後だ。
「一護さんはずるい。アタシがこんなに好きなのを知ってるくせに」
襖が開く。
そこに俯いて立っていた喜助は、手を伸ばして一護を抱き寄せた。
「それなのにアタシの気持ち無視して、他の男と結婚しようとするなんて」
腕に力を込める。
少し苦しいが、一護は我慢した。
それからはぁ、と再びため息をつく。
「…海燕さんとは結婚しねえよ」
結婚については肯定していない。
喜助が早とちりをしただけだ。
案の定、喜助は瞠目していた。
「でも、付き合ってるって…」
「付き合ってるよ? だけど結婚ってのはなあ…何か違う気がする。俺と海燕さんは兄妹みたいに育ったんだぞ」
空鶴と海燕は年が離れていて。
だから一護と海燕は同じ年頃、本当に兄妹のように育ったのだ。
「アタシは夜一さんや空鶴さんとお付き合いしたことなんてありません」
腕の力が緩んだせいで、一護は喜助の胸に手をやって、身体を離す。
喜助の顔には不満が浮かぶ。
「山本の爺さんが五月蠅いんだよ。身を固めろ結婚しろ早く子供を見せろ、ってな。顔を合わせればいつもそれだ」
一護はそれを思い出して、不快そうな顔をした。
「だから志波さんと付き合って、一時的に黙らせようと?」
一護の頭は縦に振られて。
「あの人も志波家の次期当主だろ?色々と周りが五月蠅いんだとさ。まあ、それとなく気になる人はいるみたいだけどなあ」
一護はそう言って、彼のいる十三番隊の、一人の女性を思い浮かべる。
女性の身ながら席官で、人当たりの良い女性だった。
きっと海燕とは良い関係を築けるだろう。
「浮気じゃないですか」
「そんなんじゃねえって。付き合ってる、って言ってもそういう好きじゃねえんだし」
お互いに大事な人が出来たら別れる約束。
その日が近いことを一護も海燕も分かっている。
本当に兄妹みたいなものだから、この関係は恋仲ではない。
けれど喜助は納得いかない様子で。
猫のような目を細める。
「キスやエッチはするのに?」
「バ…ッ」
一護の顔が真っ赤になることで、より目が細くなった。
「…… やっぱりしてるんじゃないですか」
喜助は一護の腕を掴んで。
自らに引き寄せる。
「だったらアタシとしましょ」
「何でそうなるんだ!」
拾われたときから随分伸びた長身を屈める。
耳元に口を寄せて。
掠れた声を出して、喜助はくすくすと笑った。
「志波さんとは兄妹のような間柄なんでしょ。親子のような間柄でも構わないはずです」
少し力の抜けた身体を、押して。
横たえた喜助は、抵抗する一護の足を押さえ込んだ。
「ちょ…っ 何押し倒してんだ! 兄妹と親子じゃ別だろ!」
「血は繋がってません。アタシは有望株ですし、結婚も子供も出来て一石三鳥」
それでも一護はばたばたと暴れる。
腕を伸ばして、喜助の身体を押しやろうとする。
その力は一個隊をまとめ上げているだけあって半端無い。
「好きです。アナタが拾ってくれたときからずっと、アナタのことだけ見てきました」
ぐいと喜助は身体を近づけて。
そっと唇を寄せる。
ちゅ、と音を立てて、それからおまけとばかりに唇を舐めた。
「嫌?」
子供らしい仕草で、首をかしげる。
一護は顔を真っ赤にしていたけれど。
「……… 嫌じゃねえよ」
はあ、とため息をついた。
けれどその目尻は赤い。
「じゃあ、しましょうか」
「それとこれとは別だ!バカ喜助!」
そう言った瞬間、思い切り腹を蹴られた。
押さえ込んでいたのに。
「何で!?」
容赦なく入ったそれに、喜助は若干咳き込んで。
けれど悲鳴じみた叫び声を上げるのは忘れない。
「俺は今海燕さんと付き合ってんだって、何回言えば分かるんだ」
一護は起き上がって。
けれど距離は取らない。
そのまま蹲る喜助を見た。
「でも別れてくれるんでしょう?志波さんにも意中の人がいることですし」
今すぐにでも別れてきて。
でも今はこうしていたい、と喜助は一護の腹に頭を押しつける。
長目の枯草色の髪が揺れて。
「……… はあ…どう育て間違ったかな」
一護はその頭に手をやって。
小さな子供にやるように、梳いてやった。
けれど重々しいため息をつく。
「間違うも何も、アタシは一目惚れなんです」
喜助はそのまま見上げる。
薄く開いた唇に、顔を近づけてまたキスをして。
「一護さんもそうでしょう?」
赤の他人の喜助を拾ったのだから。
きっと心の琴線の、何処かに触れたのだ。
「調子に乗るな…っ」
頬を引っ張られる。
けれど一護の顔は真っ赤だから。
喜助は嬉しくて、引っ張られたままの頬を緩ませた。