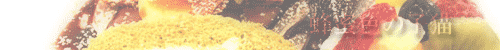
01 涙がぽろり
夜一が猫を拾ってきた。
猫が猫を拾って良いものなのか、と浦原は思ったが、彼女は元々人間だ。
子猫の珍しい毛並みは所々赤く染まっていて。
どうやら大怪我をしていたらしく、夜一が見かねて傷を癒し、連れてきたのだという。
「儂はこれから仕事なのじゃ。帰るまでその子の面倒を見てくれ」
変な真似はするな、と告げて夜一は姿を消した。
一応信頼はされているらしい。
しかしこのまま、この子猫を飼うつもりなのかな、と浦原は思った。
猫としての喋り相手が欲しいのだろうか。
「とりあえず拭いてあげますかね」
膝に抱いた、一寸たりとも動かない子猫を。
温かくしめった布で拭う。
背に大きく裂かれたような傷跡があって、おそらくこれは夜一の鬼道でも消せなかったのだろう。
浦原は手を添えた。
霊力を集中させる。
「…無理っスか」
癒しの鬼道でもっても、傷は癒えない。
ぴくり、と。
小さく猫が身じろぎした。
「…にゃ…」
起きたのか。
小さな耳を震わせて、双眸を開く。
刹那、ぽん、と白い煙。
「…………」
煙が消えた。
膝の上に座る子猫に、目を剥いた。
瀞霊廷の妖しの原因は技術開発局にあり、そう言わしめられた場所の頭であった浦原も、流石にこれには驚いた。
零れるのではないか、と思う。
琥珀色の綺麗な瞳からは水が溢れている。
涙、なのだと気づく。
ぽろぽろと落ちる。
「何処か痛むんスか?」
目の前の、襟足が長い橙の髪をした少女の。
目尻にそっと指を添えて涙を拭う。
「…ちがう…」
拙い声で、小さな頭を振った。
その頭には元の姿の時と同じ、ふさふさした耳がある。
「子猫ちゃん。泣かないで」
少女の頭を優しく撫でた。
指先で髪を梳く。
柔らかい。
「…いちご」
「苺?」
ちがう、と再び拙い声で。
「黒崎、一護…」
それがこの子猫の名前なのだとようやく悟った。
名があると言うことは誰かに飼われていたのだろうか。
「一護。泣かないで」
ぐずる幼子をあやす。
端から見れば何とも奇妙だろう。
部下が目にすれば、失神するかも知れない。
それだけ優しく。
いつもの冷酷さなんて嘘のように、浦原は一護の頭を撫でて、涙を拭ってやった。
泣くという行為は案外疲れるものらしく。
一護と名乗った少女はまた、猫の形に変化して眠った。