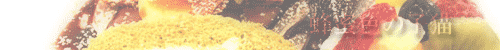
06 感情パラメータ
浦原が見下ろせば、耳がぴくぴくと揺れていた。
一護の感情に連動しているらしい。
今は楽しそうに。
予め注文して仕立て上げしてもらっていた、紺地に牡丹が散った小袖と、唐織の菊花と桜が咲いた杏色の小袖を包んで貰っている。
その合間に、下駄を物色中。
動くものと光るものに興味がある様子だ。
「これが気に入ったんスか?」
一護がじっと見つめる、金糸が織り込まれた鼻緒の下駄を、指さした。
躊躇いがちに、一護の頭が一回縦に振られる。
「遠慮しなくて良いんですよ」
じゃあ旦那さん、これも追加で。
そう告げた浦原の顔を一護は見上げる。
「…なあ」
耳が小さく震えて、そして垂れた。
「何で喜助は、俺に良くしてくれるんだ?」
「どうしてだと思います?」
知らないと一護の頭が振られた。
「泣きじゃくっていた子猫が思いの外可愛くて。あんなに必死にしがみつかれたら、きっと誰でもくらっと来ますよ」
一護の頬が紅潮する。
きっとその時のことを思い出したのだ。
泣いていた、その理由は思い出せなくとも。
「… 子猫って言うな」
恥じらいを隠すために一護は俯く。
耳は垂れていたが、けれど先とは違う様子で。
「だって一護はまだ子猫でしょ?」
大人ではないし。
猫となった夜一よりも幾分か小さい。
言われていることが分かって、一護は違う意味で顔を赤くする。
「ッだから言うな、ってんだろ!」
耳は先ほどが嘘のように立って。
引っかかれそうになった手を掴む。
轍は踏まない。
「まったく、いたずらっ子なんだから。これはしつけが大変だ」
俺はペットじゃない、と一護が喚く。
そんな一護を抱き上げた。
「分かってますよ。アタシの可愛い子ですもの」
下駄が軽快な音を立てて床に落ちる。
「何があってもアタシが守ってあげますから」
浦原は満足そうに笑う。
一護の耳が揺れる。
一度垂れて、そして上がった。