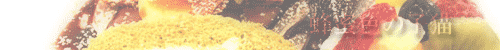
10 老人と猫
一護は巨大の霊圧に目を回したりはしなかった。
けれど浦原の背に隠れて、ちらちらと向こうを見やる。
その一部には見覚えがあって、彼らも一護を見やっているようだ。
狐と狸とそれから風車。
本人が知ったら頭を抱えそうな覚え方だ。
「何の用スか、総隊長さん。アタシも色々と忙しいんですよねえ」
「たわけ!」
髭が喋っている。
一護はしっぽのようなふさふさした髭を見つめた。
ふと目があって。
ぱっと隠れる。
「呼んだのは他でもない。その娘のことじゃ」
「夜一さんが拾ってきて、アタシが引き取ったんです。それだけでどうして隊長格が集まってるんですか」
そんな当たり前のことを。
浦原はなぜか息巻いた。
はあ、と山本のため息が響いた。
「そのものは妖しの一族の生き残り。尸魂界としても保護をしたいと思っておる」
「その話はこの子のいない所でお願いします」
山本の声が一護が届かぬように、浦原は一護を抱き上げて耳を覆ってやっている。
一護は浦原を見上げる。
その顔を見て、心配しないで、と微笑んでやった。
「アタシは上流貴族の出身で隊長で局長。後ろ盾には申し分ないでしょ」
一護の耳から手を離して。
答えるのも鬱陶しげに浦原は頭を掻く。
「失礼だが、兄に子育てなど無理であろう。よからぬ事でも思っているのではあるまいな」
「と言われましてもねえ。一護もアタシのこと気に入ってくれてるんです」
本当、失礼だ。
白哉を睨み付けて、浦原は一護を抱え直した。
「それは間違いないよ。山じい。僕なんて引っ掻かれそうになったんだから」
風車、いや京楽が口を開く。
入室したとき、やあと手を振ったのに無視をされている。
「やっぱり人徳とちゃう?ボクは撫でても怒られへんかった」
「それは猫の時の話だろう。市丸」
「藍染はんはそれでも警戒心丸出しにされたやないの」
狐こと市丸と狸こと藍染は、言い合いもとい化かし合いをしている。
それを見やって、山本の白髪の眉が上がる。
「おぬしが預かることは了承しよう。が、そのまま護廷内に留め置くつもりか?」
「死神になるかならないかは、一護に選ばせるつもりです」
だってこんな可愛い子、アタシの手から離れさせて学院に通わせたくありません。
「鬼道に似た妖術なら使えるようですけど…」
ねえ、一護。
と浦原は一護を覗き込んで。
一護の腕はしっかりと浦原の首に巻き付けられた。
「…今日はご機嫌斜めのようですから。また今度の機会に」
浦原は立ち上がる。
首には一護がぶら下がったまま。
少しばかり重いが、しっかり抱えれば問題はない。
「一護」
しゃがれた声に、一護は思わず顔を声のした方向へ向けた。
「儂は毎日茶ばかりを飲んでおる老人での。たまには此処でお茶を飲みに来てはくれまいか?」
え、何処が。
そんな声が聞こえた気もするが。
喋るたびに髭が揺れている。
しっぽのようだと一護は思う。
その髭に一護は手を伸ばしかけて。
当然届くはずはないけれど。
「…… うん」
しっぽのような髭に触れられるかもしれない、と。
一護は浦原を見上げて、承諾を取り、それから小さく頷いた。