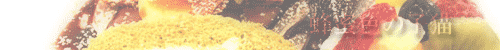
13 刺青男's
橙色の猫は、一護、というらしい。
らしい、というのは、ルキアから聞いたからだ。
橙色した猫は、どうやら人間らしい。
猫に転身出来る能力を持っているらしいが、恋次は人間姿の一護を目にしたことはなかった。
「…あ」
いちご、と恋次はうっかり発音を違えてしまった。
「…ちっちぇえな」
背丈はルキアよりも小さい。おそらく冬獅郎ぐらいだろう。
恋次は思ったままの言葉を口にした。
口は災いの元。
「何だお前!!」
息が荒く。
幾分も大きな恋次を睨みつける、小さな子供。
あちこち撥ねた橙の毛は柔らかそうだった。
擬音を付けるなら。
うがー!!
と言ったところか。
迫力はない。
「おーい阿散井」
後ろから声。
修兵だ。
「………… なんだ、このチビ」
恋次の肩から覗き込むようにして、その先を見やった修兵もまた、思うがままのことを口にした。
子供の耳が、ぴんと立つ。
「俺はチビじゃねえ!!」
どう見たって小さい子供は、幼い仕草で。
そうだそうだ、と援護射撃しているのは、肩に乗ったぬいぐるみ…?
ひょい、と恋次は猫を持つかのように。
喚くぬいぐるみをつまみ上げる。
ぐえ、と悲鳴。
「コンを返せ!」
「痛ぇ!」
どうやらぬいぐるみの名前はコン、というらしい。
子供は恋次の膝を蹴った。
地味に痛い。弁慶だって痛がる、その場所だ。
思わず恋次は手を離して、ぽとりとぬいぐるみは子供の頭に落ちる。
「つーか、お前その耳本物?」
あ、と恋次が咎める声を上げたのも聞かず。
修兵は子供の、人間らしからぬ耳に手を伸ばした。
隊長会議に出席したはずの東仙隊長から聞いていないのか、と恋次は思ったが。
かの人は盲目だ、一護がどのような姿をしているのか、知らないのだろう。
「いたッ!」
修兵は、遠慮無しにその耳を引っ張った。
生えている、と思わなかったからだろう。
「ちょ、檜佐木先輩!やりすぎですよ!」
本気で痛がっている子供と、恋次の声に修兵は手を離す。
子供の手は、庇うかのように耳を覆う。
ぐすぐす、と涙ぐませた。
「大丈夫か?」
瞳に浮かんだ涙がこぼれ落ちる。
恋次は中腰になって、優しく頭を撫でてやろうとした。
「触んな!眉毛野郎!」
今度は頭を庇うようにして。
一護は恋次を睨み付けた。
可愛くない、子供だ。
ぬいぐるみも負けじと、喚いている。
「変な眉毛しやがって!」
「ぷっ」
一護の言葉に修兵が笑う。
人のことは言えない刺青を入れているくせして。
「お前もだ!このロクジュウキュウ!」
「んだとテメ!69って意味分かってんのか!」
分かっているはずもないだろう。
穏健派の九番隊にいながら、実は短気な修兵。
子供相手に怒鳴り散らす様は大人のやることとは思えない。
「第一変な耳つけやがって…猫耳プレイってか!趣味悪ぃな!」
そんなプレイを子供がやると思うのか。
恋次は内心そう思った。
一護の目に、涙が溜まっている。
「おいバカ檜佐木。怒鳴ってんじゃねえ」
泣き出すか。
そう思った瞬間、修兵の頭から痛そうな音。
「…阿近」
「あこんさんっ」
ひょいと修兵の後ろから現れた男に、一護がしがみついた。
顔見知りなのか。
そういえば一護は浦原の養い子であるというから、面識くらいあってもおかしくはない。
「何だよ阿近。猫耳つけたのはお前か。この変態」
「それ、局長の前で言えよ」
局長。
それは十二番隊隊長を指す言葉。
一気に理解した修兵は真っ青になっている。
「この男に虐められたのか。可哀想に」
阿近の手が一護の頭に触れる。
警戒心もなく、一護は触れさせていた。
「……なんだその違いは」
修兵もそう思ったらしい。
ぎり、と悔しそうに歯がみする。
なんかんだいって、修兵も一護のことが気になっていたのだ。
「…〜 69、覚えてろ」
次はぎったんぎったんにしてやるからな!!
可愛らしい顔して口悪く、一護が叫んだ。
叫んだ後、踵を返して走り去る。
阿近が笑う。
「檜佐木。相当嫌われたらしいな」
心底愉快そうに阿近が笑うと、修兵は悔しそうに唇を噛む。
そして思い出す。
「もしかして、あのときの猫か…?」
今更気付いたのか。
恋次の心の内のつっこみを知らないまま、修兵は一護の後ろ姿を見つめた。