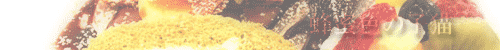
14 境界線
一護の目の前に現れた女性は、一護が未だかつて見たことないほどに、美しかった。
艶やかな黒髪が、彼女が笑うたびに揺れる。
妖艶な、紅を引いた唇が上品な弧を描く。
「ふむ…それで、そなたは妾が何なのかが気になるというのじゃな」
夜一と同じような口調。
だが、それ以上の上品さを持って。
女は、見覚えのある扇で口元を覆う。
それは、浦原がよく手にしている扇子だ。
一護はぴん、と真っ直ぐにしっぽを立てる。
女はくすり、と笑みを零した。
「そうじゃの…何と言い表せば良いものか…」
勿体ぶって言う女に、一護は歯がみをする。
その仕草さえ、女の笑いを誘うのだ。
「喜助は妾のものではないが…」
喜助、と下の名で呼ぶことに一護の耳は、これでもかと言うほど立ち上がり。
夜一も確かに浦原のことを、喜助と呼ぶが。
この女性と浦原が思いの外、親しいことがうかがい知れる。
「妾は喜助のものゆえ…」
要はそういうことじゃ、と女は言った。
一護は、瞳いっぱいに涙を浮かべる。
触れてしまえば、こぼれ落ちそうなほど。
くす、と女は笑った。
愉快と笑う。
はあ、と第三者のため息。
「……紅姫……」
肩を落として、浦原は目の前の女性にそう言った。
その前に、一護を抱き上げる。
一護の機嫌は一度曲がってしまうと、なかなか元には戻らないからだ。
「まったく、良い趣味とは言えませんよ」
彼女の悪いところだ。
ただ、一護があまりに面白い反応を返すから、からかっているだけのことなのだ。
一護は、浦原の腕の中で暴れた。
陸に上がった魚が撥ねるように。
目がつり上がっていて、本当に怒っていることが知れた。
「子供をからかわないで下さいよ」
浦原は、一護の耳を包み込むようにして、頭を撫でる。
可愛らしい嫉妬だ。
それは、浦原を不快にするどころか、何処か心地よい気分にさせる。
「子供じゃねえよ!」
一護の手が、死覇装の袂を引く。
思いがけない一護の攻撃に、浦原はおっと、と声を漏らし体勢を崩した。
「…………」
浦原は瞠目した。
目の前には、橙色の生き物でいっぱい。
琥珀の目は閉じられていて、色素が随分と薄い睫毛は長いな、と浦原は思った。
「ほほう…」
紅姫は、意地悪く笑った。
一護にではない。
拍子抜けした男の顔を見て、紅姫はまた、愉快そうに笑った。
「ん……」
驚いて、開いていた唇に柔らかな舌が滑り込んでくる。
あまりに拙い動きに、浦原は息を漏らした。
確かにこれは、子供がするものではないがどこで覚えてきたのだろう。
「ふふ…妾は失礼させてもらうとするか」
紅姫はそう言って姿を消した。
あとで間違いなくからかわれるな、と浦原は思った。
舌を、その先で舐めてくる。
子猫がミルクを舐めるように。
「んん…!」
浦原はふと、意地悪をしたくなった。
一回りも大きな舌で、絡め取る。
逃げをうっても逃げ場などない。
「…や…っ…」
息をつく暇さえ与えずに。
羽織を掴む手に、一層力が込められたかと思うと、それが嘘のように抜けていく。
溜まっていた涙が、堪えきれずに零れた。
「はぁ…っ」
息が荒い。
一護の耳は、ぺたりと伏せられている。
それを浦原はもう一度、優しく撫でた。
「… 子供じゃ、ないからな!」
息を整えながら、一護は叫んだ。
何処か満足そうに。
けれど恥ずかしそうに目尻を赤くして。
「かーわいい」
精一杯背伸びをしている。
キスだけで精一杯の一護には、まだ早い。
しっぽを優しく握ってやれば、くたりともたれ掛かってくる。
「ああもう」
どうしてこんなに可愛いのだろう、と浦原は悶えた。
小さな身体を抱き締める。
もう少し大人になってくれれば、と思うことはないわけではないが、子供らしい幼さも一護の魅力だ。
「一護も、アタシに一護をちょうだい?」
口外に、自分は一護のものだと告げて。
一護がふいに頬を膨らませる。
何か気に食わないことでもあったのだろうか。
「… 俺は喜助のもんだと思ってた」
浦原は破顔して。
ふぐのように膨らませたその頬に、音を立てて口付けた。