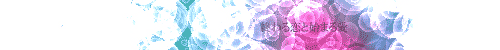
好き、だった。
「今日はぱっと、飲みましょうよ」
乱菊は、一護の腕を掴んだ。
彼女のように綺麗だったら良かったのに。
目を瞑ると、今でも思い出す。
酷く無愛想な彼は、けれどとても優しい。
『別れよう、一護』
優しい声音。
嫌だ、なんて言えなかった。
いつか綺麗な女の人が。
自分が居た場所に、立つのだろうか。
「斬月って男も見る目ないわ!」
一護よりも乱菊の方が、苛立っている。
酒癖の悪い彼女は一護に酒を勧める。
一護には飲めない、日本酒の匂いが鼻を突く。
『お前は酒が弱いのだから』
そういって介抱してくれる。
冷たくて大きい手を思い出した。
「ああ、一護っ 泣かないの!」
堰を切ったように溢れる。
だってこんなにも悲しい。
好きだよ。
今でもあんたが好きだ。
*
頭が痛い。
割れそうなほど。
酒を飲んだ翌朝はいつもそうだ。
気持ち悪い。
そう言うと、額に触れる手があった。
「………う…」
枯れきった声に、一護はゆっくりと意識を浮上させる。
一護は寝返りを打った。
触れる、もの。
「…なに…」
人の肌。
温かい。
「!」
腕が伸びる。
男のものだ。
引き寄せられる力は、強い。
「ざん、げつ……?」
一護はすり寄った。
堅い胸。
汗の臭い。
「違う男の名前、呼ぶの…?」
低く掠れた声は、甘い。
違う。
「?!」
一護は飛び起きた。
腕から這い出して、布団からも這い出す。
暗い視界の中、目に入った男に見覚えは、ない。
「だ、誰だっ」
「朝から良い眺めですね、一護さん」
腕を引かれる。
閉じこめられて、胸に押しつけられる。
「勝手に、人の家に……!警察呼ぶぞ!」
「人の家って、ここはアタシの家っスよ」
「お前誰だ!」
手で胸を押しやる。
そこで気付く。
何も服を着ていない。
「…何も… 覚えてないんスか…?」
自身の胸に手をやる。
着ていない。
布一枚さえ。
「!!?」
目を白黒させた一護に、男はため息を吐いた。
呆れている。
「昨日酒屋で、意気投合したんスよ。自己紹介もしたはずですけど…」
のっそりと身体を起こす様は、大型の肉食獣のようだ。
整った顔をしている、と思った。
「アタシは浦原喜助。へべれけになった一護さんを、あの場所においてはおけなかったから、連れて帰ったんですよ」
だったら何故お互い裸なのだ。
一護はそう視線に載せた。
「帰って来るなり、誘ってきたのはあなたですよ?どなたと勘違いしていたかは知りませんが」
きっと。
斬月だと思ったのだ。
この男のことだ、優しい言葉を掛けたのだろう。
だから勘違いした。
昨日と変わらぬ日常が送れるのだ、と勘違いした。
「…悪かったな」
シーツを掴んで、身体に巻き付ける。
身につけていたはずの服はこの部屋にないようだ。
「服は洗濯してますよ」
一護の思考を読んだように、浦原はよどみなく言った。
また、引き寄せられる。
「もう一回しない?」
「しない!」
近づく無精髭の生えた顎を押し退ける。
何なんだこの男は。
一晩の仲(文字通り)というのに、馴れ馴れしい。
「じゃ、お風呂に入りましょうか」
浮遊感が襲う。
浦原が突然起きあがり、一護を抱き上げたせいだ。
落とされそうになって、首にしがみついた。
「積極的っスね」
「! 違う!ていうか下ろせ!!」
「駄目です」
暴れるも、落としますよ?という声に思わず大人しくなる。
そんな必要ないのに。
いつもより視線が高い。
けれど、斬月に抱えられたときよりも低い。
それは浦原が、斬月よりも背が低いから。
決して低いわけではない、むしろ高い部類にはいる浦原よりも、断然斬月の方が背が高かったから。
突然大人しくなった一護を、不審そうに浦原は見た。
「その斬月さんって、そんなに良い男だったんですか?」
黙り込んだ一護は、そのまま黙ったまま唇を噛んだ。
何故、斬月のことを知っている。
いや、酔ったついでに顛末を話したのか?
「お前には関係ないだろ」
「さ、お風呂に到着っすよ」
暖房の入った脱衣所に下ろされる。
といえ、脱ぐものなんてないのだから、用はない。
えっと、一護が戸惑うと、背中に浦原が触れる。
「入って。一緒に背中流しっこしましょうよ」
「しねえよ。って、ちょ…っ!」
風呂場に押し込まれる。
なんて強引な男だ。
「はい。目瞑って」
シャワーのノズルの影。
目に水が入って欲しくない。
そう思い、思わず目を瞑る。
優しい手つきだ。
慈しむような手。
宝物を触るように、触れる。
斬月もそうだった。
彼は一護の父親の部下で、幼い頃からお世話になっていた。
彼のことを好きだ、と思ったのは高校の時。
幾人かの男と付き合って、違うと思った。
斬月が他の女性と話していると、酷く苛ついた。
思いを告げたのは、一護のほうからだ。
だいすきなひと。
子供の頃からの思慕が、恋愛感情に変わることに違和感なんて覚えなかった。
上司の娘。
だから斬月は一護の気持ちを断らなかったのだろうか?
キスを強請ったのも一護から。
抱いて欲しい、と迫ったのも、何ヶ月経っても進展しない関係にやきもきしたから。
彼は、一護が望むものを与えてくれた。
「ふ…っ」
頭を洗われる。
その優しい手つきに斬月を思う。
裏を返せば、一護が望んだもの以外に、与えてくれたことがあっただろうか。
息を殺した。
震える肩に、気付かないはずなんてないのに。
シャワーの水が、髪に降り注ぐ。
涙も。
この水と一緒に流れてしまえば、良いのに。
「一護」
歪む視界は、水?
泡はもう、完全に流れきったはずなのに。
目が痛い。
「関係ない、なんて嘘だ」
強い腕に、捕らわれる。
壊れてしまう、そう感じるほどに抱き締められる。
「アナタのことが好きだから、関係あるんです」
呼吸が出来ぬほど、口付けられて。
分からなくなった。