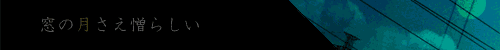
恋次は一護を見つめた。
正確に言えば、その腰の辺りを。
もっと言えば、太ももあたり、布と一護の肌の境界線を。
「現世の袴ってのは、丈が短いな」
一護はその台詞を受けて、恋次の視線を追っている。
「袴じゃねえよ。大体何処見てんだ」
後でルキアに聞いたところ、せくはら、というらしい。
せくしゅあるはらすめんと。
発音が難しい。
まあ確かに。
死覇装に隠れて普段見えない女性の太ももを、凝視するというのは失礼だ。
恋次も年頃だし。
少し胸が高鳴ったのは否定しない。
「ルキアや松本さんも着てるだろ。スカートって言うんだよ」
現世では恋次の思う着物や袴を着ている人は少ない。
女性はやたらと露出が激しくて、一護のスカート丈なんて序の口だ。
ルキアもそのくらいだし、乱菊に至ってはポロリがありそうだ。
ふと。
「だったら下はふんどしじゃねえのか?」
ぴらり。
恋次は疑問を消化するために一護のスカートとやらをめくった。
「! ブッ殺す!」
赤くなった一護に殴られた。
意識が遠のく。
下はふんどしではなかった。
あれは、ぱんてぃ、というらしい(一角情報)
響きがいやらしいな、なんて。
後の恋次はそう感じるわけだが、今の彼を支配するのは純粋な痛みだけだった。
*
一護から殴られた頬は腫れている。
おかげで授業を受けることが適わなかった。
転校早々おさぼりだった
『それは貴様が悪いぞ。女性のスカートをめくるなど言語道断だ』
屋上で屍と化していた恋次を発見したルキアは、事情を聞くなりそう言った。
追い打ちのように殴られた。
そして重々説教をされてしまった。
「おや。居候殿。随分と遅いお帰りですな」
恋次は大柄な男を見上げた。
居候殿、なんて刺々しい名詞。
「これでは三時のおやつは差し上げられませんな」
完璧な子供扱い。
別に鯛焼き以外で甘いものが好きというわけでもない。
恋次は内心怒っていたが、それを表情に出すことはなかった。
それでは飯にありつけないおそれがある。
店内に消えていくテッサイを追う形で、恋次は横木を跨いだ。
「あれ、一護が来てんのか?」
そこに見覚えのある靴が。
「黒崎殿なら先ほどおやつを食べにいらっしゃいましたよ」
ちょうど良い。
今日のことを謝っておこう。
テッサイの後について、今をくぐると。
「あ、居候。遅えじゃねえか」
ジン太という生意気な子供がそう言ってきたので、恋次は鋭い目つきで見やった。
怯んでいる。
やはり餓鬼だ。
そばには雨という少女もいる。
だが何処にも目立つ橙の少女の姿がない。
「一護は?靴あるなら居るんだろ?」
「黒崎さんなら、店長のお部屋です」
ボソボソと小さな声で雨が答えた。
少し遠慮しがちに。
「? そうか、有難よ」
恋次は居間に出した顔をすぐに反転させて、浦原の部屋がある方へ向けた。
当然足も。
居候殿、そちらは。
そんな声も聞こえてきたが無視をする。
大体そのあだ名で呼ぶのは止めろ。
「俺は犬畜生じゃねえっての。こき使いやがって」
浦原もそれを咎めないし、居候さんなんて不愉快なあだ名で呼んでくる。
何の恨みだ。
「大体一護の奴も。おやつに釣られるなんて、餌付けされてんのか」
恋次が浦原商店でお世話になって早2週間が過ぎたが。
その合間にちょくちょく、一護は此処へ顔を出しているようだ。
一護は死神としての術を浦原に習ったと聞いた。
所謂師匠と弟子ってやつだ。
おやつのついでに特訓でも付けて貰っているのか。
今も地下にあるという特訓部屋にいるのだろうか。
恋次はそう考えながら歩いているとあっという間に浦原の部屋に着いた。
そう広い家というわけでもないし。
部屋からはぼそぼそと、小さな声が聞こえてくる。
地下の特訓部屋にいるわけではなさそうだ。
恋次は勢いよく襖を開けた。
「おい一護」
はっきり言って趣味を疑う羽織が目に飛び込んできた。
一護の姿が見えないが、まあその羽織に隠れているのだろう。
「さっきは悪か―………」
ぴちゃと水音がして。
「う、わああっ?!」
一護の、叫び声。
羽織が体勢を崩したせいで、目立つ橙の髪が覗いた。
「朽木さんから人の部屋開けるときは伺ってからって、教わらなかったんですか?」
ハァ、というため息が聞こえたが、羽織…いや浦原はこちらを向こうともしない。
代わりに一護が立ち上がっていて。
右手の甲で唇を押さえて、左手は上着を掴んでいた。
はだけてる?
「お、俺、帰るっ」
顔をこれでもかと言うほど赤らめた一護は、風のように恋次の脇を通っていった。
浦原がこちらに振り向いた。
その瞳は剣呑だ。
まさか。
「あーあ。一週間ぶりに、いちゃつけるはずだったのに」
「いちゃ…」
いちゃいちゃ。
それは恋人同士が戯れる様を言うのではなかったか。
「何処かの居候さんが住み着いたおかげで、一護さんは、なかなかさせてくれないし…」
まあ必死で声を抑える一護さんも可愛いんですけどねえ。
浦原はうっそり笑った。
だがその笑みが嘘のような、重い霊圧が恋次の身体にのし掛かる。
「人の恋路を邪魔する奴は、窓の月さえ憎らしいって言いますし」
つまり、自分は一護と浦原がいちゃついていたのを邪魔したわけだ。
それは不可抗力です。
恋次は心の底からそう叫びたかったが。
「一回、さっくり刺してみた方が良いですかね?」
杖を構えてにっこり笑う浦原に、そんなことを言えるはずもなかった。