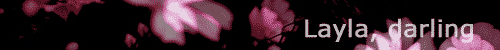
どこでもいっしょ。
昔そんな名前の付く、ちょっとおいしそうな名前の付いた白い猫が登場するゲームがあった。
一護とその兄は、同じ時期に、同じ母の腹に宿った。
いわゆる双子という奴だ。
だからいつでも、どこでも一緒だ。
母の腹から出たのも一緒なら、はいはいも歩き始めも一緒。
一護が何処かを怪我すれば、兄も同じ所に怪我をするし、どちらかが風邪を引けば、もう一方も風邪になる。
小中も一緒で(まあこれは当たり前)、高校も一緒。
この年になって驚かれるのは、今も一緒にお風呂に入っていたり、一緒に寝ていたりすること。
一緒にお風呂にはいるのは、一護にも抵抗があるが、なんだかんだ流されてしまう。
眠るのは一人で寝るよりも二人で寝る方が暖かい。
たまに二卵性か、と思うことがある。
それほどそっくりで、兄が考えていることは全て一護に分かったし、兄も同じ。
本当に同じ母の腹から出てきたのかと思うことがある。
一護を害しようとする輩が出てきたとき、兄は酷く凶暴になる。
兄の考えていることが時々、わからなくなる。
好きだ、といって一護にキスする。
一護も兄のことを好きだったし、幼い頃はよくキスをした。
愛してる、といって一護を愛撫する。
好きが愛しているなのかよくわからなかったし、兄妹なのにそれは拙くないかと思っている。
「なあっ。あ、にき」
覆い被さる兄に、あがった息はそのまま、一護は声を掛けた。
兄は動きを止めない。
一護の胸の飾りを噛んで、指で最奥をかき乱す。
「何だよ。もっと奥触って欲しいのか?」
「ひっ…う」
指を伝う。
奥を、一護が悦いと啼く場所を突いたら、悦いと言わない一護の口の代わりに溢れる。
元々は一つだった。
魂も、身体も。
それを無理矢理分けられてしまった。
だから一つになる。
元に戻るため。
これは必要な儀式。
一護に恋人が出来た。
高校生の一護と交際するのにはちょっと年が離れすぎてはいないか、と思うくらいの社会人。
それに競うような形で、兄にも恋人が出来た。
相手は不特定多数で、共通点と言えば一護とは正反対の、女らしいなよなよとした女子大生。
けれどこの関係は続いている。
一護がどれだけ恋人に抱かれようと、兄がどれだけ女を抱こうと、変わらない。
「誰?ああ、この前話してた妹さん?」
甲高い声だ。
一護の、女にしては少し低めの声とは違う。
兄の腕に豊満な胸を押しつけた頭の悪そうな女だ。
一護がこの前みた人とは違う。
「顔は良く似てるのね。でも、貴方みたいな刺々しさがないわ」
頭の悪そうな女は続けた。
「彼氏さんともとてもお似合いね。良かったわね、お兄さん」
地雷。
馬鹿な女は兄の腕から振り払われた。
そして驚いた顔で兄を見る、この光景には慣れている。
妹である一護にお世辞を言う必要はあるのか、馬鹿な女達はおべんちゃらを使って地雷を踏む。
「おい兄貴。あの人放って良いのかよ。喚いてたぞ」
「行きずりの女だ。そのうち違う男でも拾うだろ」
兄は女をおいて、一護に付いてきた。
一護は恋人と兄と、二人の男に囲まれる。
端から見たらどういう関係なんだろうか、これは。
「一護さんはアタシとデートしてたんですけどねえ。どうしてこうなるんでしょ」
そういって浦原は一護の片腕を浚う。
もう片方は兄の腕の中。
「不満なら帰れ。俺は一護とホテルにしけ込むからよ」
「誰が行くか」
「そうです。ホテルは今からアタシと行くんです」
「行かねえよ」
浦原は、一護と兄の関係を知っている。
気づかない方がおかしい。
兄は気づかれるよう、わざと跡をつける。
それは普通出来ないようなところの噛み傷や歯形だったり、鬱血だったり。
浦原は気にしていない。
気にしてはならない。
ただその痕が残っている時はいつも、一護を激しく抱く。
止めて、と言っても聞いてはくれない。
ただ乱暴に掻き抱き、貪る。
「門限は6時だ。破ったら承知しねえからな」
一護の頭を抱いて、兄は一護にキスをする。
往来の中、それは酷く目立ってしまった。
兄は気にする素振りなど見せず、手を振って去っていった。
困るのは後に残される一護だ。
「一護さん」
ほら。
「行きましょうか」
何処へ行くかなんて明白。
いつもより低い声で、一護を押し潰す。
「……」
拒否権など持ち合わせていない。
*
壁に押しつけられた。
さほど大きくない胸がつぶれて、けれど男の手に収まる。
「ッ、やぁあ!」
後ろから、双丘を割られて、押し入られる。
いつもより高ぶったそれは、少し前まで一護の口の中にあったものだ。
「ぁあ、も…おっ」
「もっと?」
「ひぁあっん」
たとえベッドに崩れても、無理矢理起き上がらされて貫かれた。
腰を掴まれて、揺さぶられる。
頭までぐちゃぐちゃになりそうだ。
「うら…ッ」
「アナタは、アタシのものだ」
よりいっそう貫かれて、何も考えられなくなった。
頭が真っ白になる。
それはまるで兄の頭髪のようだ、と一護は場違いにもそう思った。
一護は兄のものではない。
兄も一護のものではない。
一護も兄も同一だから、どちらがどちらのものになる、なんてない。
だから一護は浦原のものだ、浦原だって知っている。
けれど浦原は恐怖する。
分かたれたものが一つになる日が、酷く怖かった。
*
朝焼けが兄であるように、夕暮れは一護だった。
冬は日が暮れるのが早い。
6時にはまだあと30分ほどあるが、もう5分もすれば空は闇になるだろう。
「じゃあ一護さん。また、明日」
「明日は学校だ」
「学校が終わったら、アタシん家に来てくださいな」
柔らかな白い手袋を、そっと握られる。
一護も灰色のそれをそっと握った。
恥ずかしがり屋の一護の、精一杯の返事。
「じゃあな」
玄関が開く。
それと同時に浦原は一護の唇に自分のそれを合わせた。
「一護。冷えるから中入れ」
「… おお」
見られていた。
当たり前だ。
そのように浦原がわざとしたのだから。
兄と同じ色の手袋を取って、冷たいその手を取った。
家の中に居たというのに、こんなにも冷たい。
「ドラマの再放送、撮っておいたからな」
「あ、サンキュー!頼むの忘れてて、どうしようかと思ってたんだ」
「ああいうドラマなんて見て面白いか?」
「兄貴が見る昼ドラよりは面白いと思うけど…」
二人で居間に入る。
妹たちは居なかった。自分の部屋に戻っているのだろう。
「昼ドラは面白いぞ。ドロドロしててな。そうだな、俺とお前の関係に似てるな」
「ドロドロ…」
「いつかあの野郎も包丁もって、"アタシと死んでください"って言い出すぜ」
「…なんか洒落になんねーかも」
兄は馬鹿にしたように、少し高めの声で口調を真似する。
それではただのオカマだ。浦原はただオカマ言葉を使うだけだ。
一護は肩をすくめた。本当に洒落にならない。
情事の時、本当にそう言われた後浦原に首を絞められて、達してしまったことを思い出した。
自分は変態かもしれない。それとも色狂いか。
「まあそうしたら俺が返り討ちにしてやるけどよ。安心しろ」
「安心していいのか?俺は」
兄は声を出して笑った。
一護も肩を震わせて笑った。
無性に面白かった。
テレビはニュースを映し出す。
恋人に振られた男が逆上して、その恋人を刺し殺したのだと。
「洒落になんねえな」
一護はもう一度、肩を震わせて笑った。