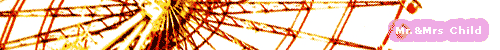
自分は子供を産んだっけな、と一護は自問した。
いや、産んでいない、と自答した。
ではこの目の前の幼児は何なのだろう。
恋人にうり二つの、つまりは彼を小さくしただけの、幼い頃はこうだったのだろうなという幼児。
うたた寝をしていた一護の膝に、いつの間にか居たこの子供は、一護が目を覚まして少し体を動かしたにもかかわらず、身じろぎ一つしない。
「もしかして浦原の隠し子?」
あり得る。
夜一は、一護と出会う前まで彼は女癖が悪かった、と言っていた。
この子供の年は4歳くらい。
一護と浦原が出会ったのがちょうど3年前だから、この子供が生まれていてもおかしくはなかった。
その後に出来たかも知れない、という可能性は一護の頭にはない。
彼は天才であったが、一護に関してはバカだった。
「…可愛い」
例え浦原に似ていても可愛い。
一護は金色の髪をすいて、膝の上で眠る子供を見つめた。
浦原と結婚するのは正直ごめん、というより一護にそんな心の余裕がないのだが、子供は少しだけ欲しかった。
そんなことを少しでも漏らせば、どうなるか分かっているので言わないだけだ。
「…ん…?」
「悪い。起こしたか?」
震わせた身を起こした子供の顔を、一護は覗き込んだ。
浦原にそっくりだが、これは浦原ではない。
「アナタは?」
「黒崎一護だ。…お前は?」
「浦原喜助です」
「… アイツ…自分の子供に同じ名前つけるなんてどういう神経してるんだ…」
舌足らずな声は、いつもの彼よりも幾分も高い。
まさか義骸ではないだろうな?と思った一護は、少年浦原の手を取って脈を確認。
義骸ではないと判断した(しかし涅マユリの作ったネムには脈があることを一護は失念している)
「どうかしたのか?」
「阿近さん」
「そのガキ…」
ここは技術開発局の一室。
当然阿近が居てもおかしくないわけで、見知らぬ声が聞こえてきて不審に思った彼が覗き込んだらしい。
阿近は一護の隣に座っている子供を見て、目を見開いた。
「ん?浦原の隠し子かなと思うんですけど。アイツ、孕ませて捨てそうな感じだし」
なんて失礼な。
浦原がその場にいたら喚きそうな台詞だ。
子供が阿近を見た。
ちょうど一護からは見えない位置。
子供はにやりと笑っていた。
これは。
「……… いや、一護。これは局長だ」
「え?」
浦原が口をぱくぱくさせ、唇だけで言葉を伝える。
阿近は、なんて奴だと思いながら、それを一護に伝えた。
伝えなければ何をされるか。
「どうやら何かの薬を飲んで幼児化したらしい」
「でも俺のこと知らないって…記憶も、退行したんですか」
「た…ぶん」
そうだ、そう言え、と子供は言った。
正直子供にあるまじき剣幕と殺気。
それに若干押されつつも、阿近は一護を見た。
「これ、戻るんですか?いや、このままの方が俺には無害ですけど…仕事して貰わないと困るし」
いや、もっと有害だ。
阿近はそう伝えたかった。
それが出来たらどんなに良いことだろうか。
「そういえば退行後は徐々に成長する薬を開発したって言ってたような…記憶もだんだん取り戻すって…」
「…………」
浦原はにやりと笑った。
すまない、一護。
「面倒なことするな…何考えてんだ、浦原の野郎」
小さな体を利用して、お前に色々するつもりだ。
「でもまあ、この小さいのには罪はないしなあ。問題は一週間どうやって隠すかだけど…」
「それは問題ない。お前が来る前までは一週間研究室に引きこもるなんてざらにあったからな」
一護は驚いていた。
それもそうだ。
浦原は一護が来る前はほとんど研究室から出てきたことがなかったのだ。
一護が配属されて、もっぱら隊舎にいるようになって驚いたのは技局のメンバーだけではない。
「仕方ない。こいつ、家においてきます」
「一人に、なるの?」
「…え…」
一護はたとえこれが浦原といえ、まだ4.5歳の子供を屋敷に一人きりにするのに、罪悪感を覚えたのかも知れない。
浦原(子供)は、小さな顔で一護を覗き込む。
負けるな、一護!あれは間違いなく浦原だ。
阿近は心の中で叫んだ。
「う……」
「ここにいちゃ、駄目?」
「……… 分かった。でも此処は俺、部外者だから、隊舎に…」
一護の母性本能は負けてしまった。
よっこらせ、と一護は浦原を抱っこする。
「…… 気をつけろよ」
「? はい。誘拐されないようにします」
「………」
そんな子供、誰が誘拐するものか。
阿近は心底そう思ったが、何も言えなかった。