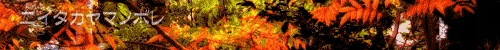
告白は体育館裏と相場が決まっている。
「い、一護、す、す、好きだッ!」
女が好きな啓吾の、一世一代の告白は、体育館裏ではなく、いつも昼食を取る屋上で行われた。
息荒く。
いつもは黒崎さん呼びだけれど、今回ばかりは下の名前で。
いやいや、今回と言わず次回からも是非。
「…ええっと?」
「俺とっ 付き合ってくれ!」
困惑気味の一護は、いつものような凛々しさがない。
時折見せる女性らしさ。
このギャップがたまらないと思っているわけだが。
「ごめん」
悦に浸っていた啓吾には、一護がなんて言ったかなんて耳に入らなかった。
「え?」
「俺、男に興味ねえんだ」
何かの聞き間違い?
俺、なんて、ちゃんと可愛らしい顔をしているのに、男らしい口調をする。
「だから俺、浅野と付き合えない。ごめんな。有難う」
そう言って、屋上のドアをくぐる一護の姿を、啓吾は見つめることが出来なかった。
ああ、今すぐ屋上から地上へ最短距離で帰りたい!
「まあこういう事もあるよ」
可愛い顔をしてスケコマシ。
親友と呼んで良い物か、けれどもいつも連んでいる、水色と書いて年上キラーと読む彼は、慰めるなんて優しい台詞は吐かない。
むしろ、楽しそうに。
「ど、どういうことだっ?!」
ああ、と水色は頭上に豆電球。
きっと漫画だったらそう描かれたに違いない。
「言うの忘れてたんだけどさ。黒崎さんって、どうもそっちの気があるらしいんだ」
初恋は、幼馴染みの有沢竜貴らしい。
ああ、だから男に興味がないのか。
いやいや、有沢は何処の男よりも男らしいし、啓吾なんて適わないくらい強い。
いや、でも有沢は女だろ。
「は、レ、レズビアン?!」
「珍しいことじゃないよ。第一クラスに一人いるじゃないか。それも凄いのが」
凄い人こと本匠千鶴の顔を思い浮かべた啓吾は、ついでに彼女が発する放送用語スレスレの言葉を思い出す。
織姫の純潔を我が手に!
なんて。
そんな一護は想像したくない。
「良い人生経験になったじゃないか。世の中には色んな趣味の人がいるんだってね」
ハハハ。
幾人もの女性を誑かしてきた水色は、やっぱり心底愉快そうに、笑った。
*
「…なあ」
「ん?何だ?」
「…えっと、その、さ」
「はっきりしろ」
言い淀む一護に、ルキアはしびれを切らした。
一護はらしくもなく、それでも口の開閉を繰り返す。
「…れ、恋次のこと…好きなのか?」
「は?」
「いや。お前、恋次と仲良いだろ?幼馴染みってのは知ってるけど…その、」
幼馴染みといえど、所詮は他人だ。
けれど恋次は、自隊の隊長に刃向かってさえ、ルキアを助けるのに動いていた。
あれは兄妹のようだ、と白哉は言った。
「別に私と恋次は恋仲ではないぞ?それにそう言う意味で好きな訳ではない。恋次とはただの幼馴染みだ」
真面目な顔をして言う。
むしろ、あやつと恋仲なんて、と言って、ルキアは身震いをした。
ルキアは演技が出来るような人間ではない。
そんなルキアは一変して、にやりという笑みを浮かべた。
「…もしや……一護、恋次の事が好きなのか?」
「ちっ違…!」
「ふふん。そうか、一護が恋次のことを……」
さらに笑みを深める。
勘違いだ!
一護は何度も首を振った。
「誤解だ!」
「照れずとも良かろう」
ふむ、恋路を手伝ってやろうではないか、と言い出さんばかりの顔だ。
ルキアはこの手の話が好きらしい。
「だから!俺が好きなのは!」
「恋次か?」
「じゃなくて、お前だっての!!」
間抜けな顔だ。
けれど一護は顔を真っ赤にさせた。
「……は?」
「………… だから、俺が好きなのはお前」
ぼそぼそ、とようやく聞こえるくらいの声音。
それはルキアが近くに寄っていたから、伝わった。
「私よりも乳がでかいくせに、何だ?これは詰め物なのか?」
「自前に決まってるだろ!つか触るんじゃねえよ馬鹿野郎!」
「野郎だと?!私は女だぞ!」
「俺も女だよ」
胸を揉むルキアの手を引きはがして、一護は息をついた。
お互いが女であることくらい、分かっている。
一緒に風呂に入った仲なのだ。
「… 私も一護のことは好きだぞ。恋次とはまた違う、一番の親友だと思っておる」
「そう言う意味で、俺は好きなんじゃねえよ」
ルキアの腕を引いた。
彼女はとても小さい。
女の一護でさえそう思うくらい。
「こういう意味で、好きなんだ」
抱き寄せたルキアの身体を離す。
だから、そっと寄せた唇も離れた。
「…ごめん」
*
「どうしたんです?浮かない顔ですねえ」
暢気な声にルキアは振り向いた。
案の定そこに経っているのは下駄男。
「……何だ強欲商人」
「ビタミン剤でも差し上げましょうか?」
そう言って彼は懐から出してきた瓶をちらつかせる。
「貴様の差し出すものなぞ受け取らん」
義骸の恨み、それを巡るあれこれをルキアは許しはしたが、忘れはしない。
第一、この変態男がまっとうな物を寄越すはずがないのだ。
「手厳しいっスねえ。……ああ、一護さんに告白でもされましたか?」
「………何故それを…」
少し頬を赤らめ、けれどその大きな目を見開いて、ルキアは浦原を見上げた。
「アタシが知らないことなんて何もありませんよン」
相変わらず表情の伺えない。
扇子で顔を隠すものだからなおさらだ。
いや、一つだけ分かっていることがある。
「アタシはいつもあの子を見ていますから。あの子がいつも誰を見ているかなんてすぐに分かるでしょう?」
一護の前に居るときは、その嬉しさを隠そうとはしない。
そうだ、この男は。
「惚れた女の眼中に、男なんてこれっぽっちも映っちゃいないなんてこと、前から知っていました」
一護の視線の先には、いつもルキアがいたから。
どれだけ骨を砕いて彼が一護を口説こうとも、靡きもしない。
「アタシはどうすれば良いんスかねえ」
ハァ、と隠れた口角は下がっているのか歪んでいるのか、ルキアには分からない。
「アナタが消えてしまえば、あの子はアタシを見てくれますかねえ?」
本気とも冗談とも。
けれど瞳に宿る不穏な光に、ルキアは足を一歩、後ろへやった。
「ルキアッ」
空気を裂くような声がして、ルキアも浦原もその方向を見た。
それが誰かなんて分かり切っていたけれど、その瞬間光が消えた。
「っもう、暗くなるから、夏梨も遊子も、心配する」
息を乱して。
一護はルキアの腕を掴んだ。
優しく、けれどその手が震えている。
一護さん、と。
その声音が優しいのも、親しみを込めて呼んでいるのもきっと一護は知らないのだ。
「ちょっとお話があるんです。二人っきりで」
目を隠す帽子をより目深に被って、浦原は一歩一護に近づく。
扇子はいつの間にか仕舞われていた。
「朽木さんはどうぞ。お帰りになって結構ですよ」
突き放すような言い回しに、一護が眉を寄せる。
おい、と続くはずの言葉を封じて、ルキアは口を開いた。
「私は先に帰っておくからな。浦原!一護に変な真似をするではないぞ」
一緒に、帰りたくないと言えば語弊があるが。
もう少し時間が欲しかったのだ。
ルキアは踵を返して走り出す。
その後ろ姿を見つめていた一護は、腕を引かれて振り返る。
そのまま店内に引きずり込まれた。
「何の用だ」
ピシャリと扉が閉じる。
眼光は鋭い。
戦いにおいて師弟の関係ではあるものの、一護が浦原を好ましく思っていないのは知っている。
「嫉妬しなくたって、別にアタシは朽木さんに気なんて持っちゃいませんよ」
ふふ、と浦原が煽るものだから、いっそう一護は不愉快そうになる。
何の用だ、と再び繰り返した。
「どうやらね、朽木さんはアナタの感情に少し、困っておられるようです」
それが何を指すのかは明白。
一護は何故、と問いただそうとしていて、けれど結論が出たようだ。
きっと、先ほどの会話で。
傍目にはそうは見えなくても、一護が狼狽しているのが手に取るように分かって、浦原は薄笑いを浮かべる。
そんなこと、分かっているのだと。
分かっていても一護の感情はついて行けない。
浦原は掴んだ腕を思い切り引き寄せる。
「ッ!」
突然のことに体勢を崩し、倒れ込んでくる一護の顔に、顔を寄せた。
そのまま唇を重ねる。
「…は、あ…な、にすんだっ!」
十分に貪って、顎に伝う唾液を舐め取った瞬間、一護の拳が飛んでくる。
それを易々と避けた浦原は、指先で自分の唇をなぞった。
かあ、と一護の顔が紅潮する。
「おや。一護さんだって朽木さんの唇奪ったんじゃないんです?アナタには咎める権利はないはずだ」
「何で、そんなこと知ってるんだ!」
浦原が一護の腕を放さないから、一護はもう片方の腕で必死に唇を拭った。
その様子に、一つ嘲笑を含んだ息を漏らす。
「アナタが朽木さんをずっと見ているように、アタシもアナタをずっと見ているんスよ」
この目にはきっと、暗い闇が宿っている。
けれど一護が宿すものは違う。
「ただ、大切にしたいというアナタの生ぬるい感情とは違っていますけどねえ」
一護よりも大きな手で、小さな顎を掴む。
異常なほどに顔が近づけて、動けないのを良いことに、舌で唇に触れる。
「アナタを汚してしまいたい」
「っ」
「アタシはね、そう思うんです。おそらく愛はそう言うものだ」
大切にしたいとは思う。
けれどそれ以上に、もっともっと、自分を見て欲しい。
愛は執着と同じ。
「俺は、そんな風には思わないっ 仮にそうだとしても、お前には関係ない!」
これまで以上に顔を赤らめて、一護は渾身の力でもって振り払う。
店内の静けさを裂くような音がして。
浦原は打たれた頬を押さえようともせず、一護ににじり寄る。
「関係あります。だってアタシは一護さんを手中に収めたいし、君を抱いて……アタシ以外、誰にも見せたくない」
「っそれでも俺は、お前なんて好きになんねえよ!!」
吐き捨てると、一護は踵を返して扉を開く。
そのまま振り向きもせず走り去る姿が見えなくなっていくまで見つめて、浦原はため息をついた。
にゃあ、と一護の代わりに入ってくるのは一匹の黒猫。
「喜助」
「手酷くフラれちゃいましたねえ」
「諦めるのか?」
黒猫は遠慮した様子もなく、座敷に上がる。
意地悪な金色の目で、浦原を見据えた。
「いいえ。アタシの感情は半端なんかじゃありませんもの」
うっそりと、鈍く痛む頬を撫でて。
浦原は笑いながら黒猫の後を追った。
*
門限まであと少し。
父親の一心が、怒り始めるまであと数分。
けれど一護は導火線に火がつくその直前に、家の門をくぐった。
「…ただいま」
息を乱して、肩で息をする。
「おかえり。一姉」
「?どうかしたの?」
いつもの仏頂面で、けれどいつもより険しくて。
靴さえも脱がぬまま、玄関で立ちつくす一護に、妹たちは声を掛けた。
「飯は、後で食べるッ」
何かあったなんて明白だ。
一護は靴を脱いで、そのまま自分の部屋へ一直線。
残された夏梨と遊子が、どうかしたのかな?なんて顔を見合わせても何ら不思議ではない。
「親父には言うなよ。あいつ、親ばかだからな」
そうやって夏梨が遊子に釘を刺しているなんて露ほども知らずに、一護は自分の部屋のドアを開いた。
「…ル、キア…」
彼女が居て当たり前だ。
ルキアは一護の家に居候しているのだし、客間がないから一護の部屋で寝起きしている。
「貴様は私を好きだと言ったな」
「………そうだ…よ」
ドアを閉めろ。
視線で促されて、一護は後ろ手に扉を閉める。
次は、座れ、と口に出され、床に座り込む。
ベッドに座るルキアの視線が上から降る。
「……それは、私に交際を申し込んでおるのか?」
「だから、その…」
そうだ。
けれどはっきり言い切れない。
駄目だ、と否定されるのが怖い。
不埒なことを。
浦原が思う、汚したい、なんて気持ちはなくても、何処か後ろめたいから。
「……いっしょ、に買い物行ったり、こうやって二人きりで喋ったり、したいなって…」
「それは友達同士でもするのではないか?」
「そうだけどさ、いや、でも違うんだよ…感覚が…違う」
いたたまれなくなって、一護は床の目に指を這わせる。冷たい。
それは一護から冷静さを取り戻してくれるような、気がする。
「ムラムラはしないのか?」
「ムラッ?!何て事言うんだよ!!」
一護は赤面した。
そんな感情はない。
耳まで赤くした一護は、その顔を隠したくて腕で覆う。
とん、と床の音。
「一護にそういう感情はわかないが、今、私は一緒には幸せだと感じるぞ」
腕を引きはがされる。
一護は視線をあげれば、そこにはルキアの顔があった。
「接吻も…そうだな。嫌ではない」
「へ…?」
ちゅ、と柔らかな触れるもの。
「柔らかいし、うむ。少しはムラムラするというのが分かるかも知れぬ」
ぺろり、と唇に濡れた感触。
一護は驚いて、驚きすぎて腰を抜かした。
「こうやって二人で話して、たまに買い物して、接吻しよう」
ルキアの両手が、一護の左手を包む。
ルキアは中腰だから、いつもより視線が高くて。
「付き合ってくれぬか?」
「……うん」
だからいつもと違う、ドキドキを覚えた。