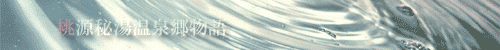
硫黄のにおいが立ちこめる煙。
一護はそれを好みはしなかったが、生まれて初めて訪れる温泉に胸を高鳴らせた。
隣にいる男が浦原でなければもっと楽しかったに違いない。
"温泉に行こう"
それを言い出したのが誰だったのか、もはや誰も分からない。
たぶん、京楽であった気がするが、今となってはどうでも良いことだ。
あれよあれよという間に計画されたそれは、各隊の隊長と副隊長が参加する大規模なものとなった。
一日といえ護廷を空にして良いのか、と一護は思ったが、その疑問は昇華されることなくこの日を迎えた。
流石に総隊長は参加せず、総隊長殿が行かないのなら、と狛村や雀部は辞退した。
なぜか二番隊の大前田は怪我をしたということで欠席した(後にこれは砕蜂のせいであることが発覚した。その砕蜂もまた夜一がいかないならと欠席した)
副隊長の一護も参加した。
本当は参加したくなかったが、浦原に(不本意ながら)ほだされた。
初めての温泉を楽しみにしていたことはこの際内緒にしておく。
(でも俺、風呂どうしよう)
一番の楽しみだが、一番の問題でもあった。
「あー素敵ッ 温泉なんて何十年ぶりかしら!」
死覇装では仕事でやってきているみたいだから、ということで私服案が可決された。
私服と言えども皆着物なのだから、対して変わらないと一護は思っていたが、乱菊の着物姿は綺麗だと思った。
「松本、落ち着けよ」
「やだなあシロちゃん。子供なんだから子供らしく楽しめば良いのに!」
「俺は子供じゃねえ!つか、シロちゃん言うなって何回言えば分かるんだッ!」
冬獅郎は怒鳴った。
一護は彼のそういうところが子供なのだ、と思ったけれど黙っておいた。
実年齢においては一護だって子供に間違いない、というかこの中で一番幼いからだ。
「まあまあ、雛森くん。日番谷くんも。せっかく羽を伸ばしに来たんだから」
雛森に掴みかからんばかりの冬獅郎をなだめたのは藍染だ。
一護は彼を非常にうさんくさく思っているが、優しい(一護にとっては胡散臭い)笑みを浮かべている。
「どうしたんスか?」
肩に掛けられた手を遠慮無く払った一護は、その手の主を見上げた。
シンプルな割には高そうな黒の着流し。
さすがは上流貴族の息子だ、と一護は思う。
似合っていると思ったが、つけあがると困るので黙っておいた。
「その着物よく似合ってますよ。流石アタシが見立てただけあります。…本当は始めに渡した着物を着て欲しかったんすけど」
「誰が着るかッ!」
「痛い!」
一護が纏っている男物とも女物ともとれるそれは、浦原から送られた物だ。
始めに送られた明らかに女物の着物は突き返した。
四楓院の館で女物を着る機会は多かったが、どうして一護を男だと思っている奴らの前で着なくてはならないのか。
本当は夜一からこの日のために、と着物を用意されていたが、なんだか浦原が五月蠅かったので仕方なく着た。
夜一には謝ったが、着ないと何かされる気がしたからだ。
「なあ一護ちゃん。そんなセクハラ隊長やのうてボクと行こうや」
「ええー。ボクと行こうよー」
「おっさんは黙っとき」
「…どちらも一護にとってはおっさんだろう」
浦原の顎に拳をとばした一護の、もう片方の手を取ったギンが細い目をさらに細めて笑っている。
京楽も負けずに(そもそもなぜ対抗する必要があるのか)一護の手を取った。
どちらもが反対側に行ったら、俺裂けるかもと思った一護であったが、そんな危機を救ったのは浮竹だ。
あんさんもおっさんやろ!とギンにつっこまれていたが、助かったと思った。
「兄らは少し五月蠅いのだ。店の者も困っているだろう」
腕を引っ張られて、顔を上げると白哉が憮然とした顔で見下ろしてきた。
白哉が周りを気遣うなんて意外だ。
「そ、それではお客様。ごゆっくりどうぞ」
引きつりそうな笑顔を浮かべた仲居が、そそくさと部屋を出て行った。
大勢と共に宴会場と思わしき大部屋に通された一護は、働くというのも大変だなとのんきに思う。
護廷の隊長格がいっこうに集ったこの場所で、平気で居られる神経なんて一般人が持ち合わせてはいないことを、幸か不幸か一護は知るよしもなかった。
*
どうせ酔いつぶれるから、と酒を飲む前に風呂にはいることになった。
この温泉は女湯と男湯、そして混浴があるという。
「混浴風呂の方が広いのねえ」
乱菊は躊躇無く混浴風呂の扉を開けた。
そこに誰かいるかも知れない、という遠慮はない。
この温泉は死神一行に今日一日貸し切りだからだ。
「どうしますか?」
「混浴と言っても男性が入ってこなければ、女湯になりますけど」
勇音の問いに、満面の笑みを浮かべたのは卯ノ花だ。
穏やかな外見に反して彼女は腹黒いところがある気がする。
みんな一緒に入ればいいじゃない!と言った京楽は七緒に沈められた。
うかつな発言は慎むべきだ。
「じゃあ、女性が先に入って、僕らは後から入ることにしようか」
東仙の言葉で決まり。
きゃーきゃーと浮き足立ち始めた女性陣は早々に男を外へ追い出し始めた。
ずっと剣八の肩にいたやちるもまた、飛び降りてその中に入っていく。
「一護くんは?一緒はいる?」
「え、えええ!?」
扉から顔を覗かせた雛森に、一護は赤面した。
一応女だが、一応男だ。
雛森だって男と思っているはずだ。
「別に構いやしないわよ。どうせアンタまだ14でしょ。あ、日番谷隊長もどうですか?」
「巫山戯るな!」
男が女風呂に入れるのは小学生までです、と一護は思った。
年が近い一護も、見た目が近い冬獅郎も、流石に拙いだろう。
冬獅郎も声を荒げているが顔は真っ赤だから、覇気に欠ける。
「え、んりょします…すみません」
「そう。残念ね」
乱菊は心底残念そうな声を出して、扉を閉めた。
中から騒がしい声がする。
小学校の修学旅行を思い出して、ちょっと混ざりたかったな、と思う一護だったが、正体がバレてしまっては元も子もない。
その後、女性があがってきた次は男の番、一護も当然はいるよう促されたが、"後ではいるから"と断っておいた。
うっかり檜佐木に引きずり込まれそうになったが、東仙の助けもあって何とか逃れることが出来た。
*
「というわけで、日頃の疲れを労いまして、乾杯です!」
言い出しっぺの京楽…の代わりに副隊長の七緒の音頭で始まった酒盛り。
まだ実年齢だって20歳に満たしていない一護は、酒のすすめを丁重に断った。
「一護ちゃん飲まへんの?」
「俺、未成年だし」
「ええやん。ボクがお酌するさかい」
すり寄ってきたギンの吐息は既に酒臭い。
正直臭いにも酔ってしまいそうだ。
あまり酒が強くないことが発覚した今、一滴でも飲めば酔いつぶれてしまうだろう。
「乱菊さんに頼んだら?」
「あかん。乱菊は酒豪やもん。人に飲ませるぐらいなら自分で飲むやつや」
確かに。
京楽と酒飲み仲間という乱菊はさほど出来上がることもなく、量をこなしている。
隣には出来上がった恋次とイヅルが酔いつぶれていた。どうやら彼らは酒に弱いらしい。
「だったらお酌してくれないかな?」
いつの間にか傍に寄っていた藍染は、手に持ったとっくりを一護に手渡してくる。
その後自らの猪口を差し出してきたから、一護は仕方がないとばかりにその小さな器に酒を注いだ。
「浦原の下で働くのは大変だろう?」
「…まあ」
「五番隊に入らないかい?雛森くんがいるから副隊長は無理だけど、三席を用意するよ」
「遠慮します…」
藍染は酔っぱらった素振りがない。
どうやら酒にはめっぽう強いらしい、というのが雛森の調査結果。
「アタシの一護さんに気安く触らないでくれません?」
「一護くんは君のものではないと思うよ」
しかし酒のせいで地が出ているような気もする。
浦原と藍染に挟まれた一護は、慰安旅行のはずなのに癒されないと一人呟いた。
それから2,3刻後。
この部屋の状況を四文字熟語で言うのなら、死屍累々がふさわしいだろう。
酔い潰れたのが隊長なら副官が、副官なら隊長が、それぞれ引きずっていく。
白哉は恋次を運ぶことを嫌がっていたので、同僚の檜佐木が彼を連れて行くことになった。
女性陣は二人で一つの部屋。
男性陣は互いが嫌がらなければ、同じ隊同士で寝ることになった。
白哉は貴族の機微という奴で、一人部屋。
副隊長が女性である藍染もまた一人部屋で、追い出された形となった恋次を引き取ったのが冬獅郎だ。
やちるは剣八と寝るということで、その四つが例外となった。
冬獅郎はまた、乱菊とその同室の雛森にからかわれていたが、酔っぱらっていて何を言っているのか分からなかった。
不憫だ。
浦原と一護も例外ではない。
白哉以外は皆、一護が男と思っているから、たとえ浦原が変態であろうとも、同室になるのは自然の流れ。
一部浦原とは別室に(むしろ一護を我が部屋に)という動きもあったが、なぜか鎮圧されてしまった。
正直一護も一人部屋が良かったが、我が儘を言うのは憚れた。
部屋にはいるとなぜか布団がくっついていた。
犯人は目の前の男らしい。
近づいたら殺す、と一護と唸って、布団を話し広い部屋でそれぞれ端で寝ることになった。
*
寝たふりをしていた一護は浦原が眠っていることを、遠目で確認して立ち上がる。
汗はかいていないし、酒だって飲んでいないが風呂に入りたい。
それにここは温泉宿、温泉に入らなくてどうするというのだ。
「… 誰もいない、よな?」
一護は混浴と札の下がった扉を開けて、その中を見渡した。
煙が立ちこめているがそこに人の気配はない。
男湯に入っては、誰かが来たときに困る。
女湯に入っても、一護は男になっているから困る。
まあ混浴なら、誰が入ってきても困らないはずだと(実際は困るが)思い至った一護は、混浴に入ることにしたのだ。
「…ふう…」
体を洗い流して、一護はお湯につかった。
胸にはきっちりタオルを巻いているが、いつもつけているさらしを外すというのは気持ちが良い。
阿近が開発してくれたさらしは、昔つけていた包帯のように圧迫しないものの、つけないに越したことはない。
四楓院の館の風呂よりも広い。
夜一はよく一護と風呂に入りたがったから、滅多に一人で入ることはない。
それよりも広い風呂を独り占め。
子供が広い風呂で一人っきり、という状況で考えることは一つしかない。
「泳ぎてーなあ」
「泳げば良いじゃないっスか」
「!!?」
一護の独り言は広い風呂の壁にこだまして終わるはずだった。
ましてや答えが返ってくることなんてあり得ない。
振り返った一護の視界に入ってきたのは、湯煙に霞んだ浦原の姿。
腰にタオルを巻いていてくれて良かった。
なんてことはどうでも良い。なぜこの場に彼が居るのだろう!
確かに彼は眠っていたはずだ!
「な、な…」
「大声出すと皆起きてきますよ。響くんですから」
口を開閉させるだけの一護は、笑みを浮かべてこちらへ寄ってくる浦原を止められるはずがない。
先に体洗ってから入れよ、とか、つかお前男なんだから男湯入れよ、とかつっこみたいことは多いがつっこめる状況ではない。
「ッ何でここに居るんだ!」
「まだ風呂に入っていないことを思い出しちゃいましてね。ついでに、一護さんがいなかったからどこに行ったのかな〜と」
ついでは風呂に入ることを思い出したことだろう。
一護は響かぬよう小声で叫んだが、それが浦原を近くに寄らせる原因の一つとなった。
声が聞き取れない、と近寄ってきた浦原だが、そんなこと無くとも始めから近寄ることしか考えていなかったはずだ。
「寄るなッ」
俺は女だぞ!
浦原はにじり寄ってくる。一護もじりじりと後退した。
背に当たるのは風呂の縁。
もはやこれまでか。
浦原の秀麗な顔が近づく。
煙で見えない、なんて言えないほど鮮明に近い。
キスされてしまう!
一護はそう思って堅く目をつむった(それが逆効果であることを一護は知らない)
「そのくらい知ってますよ。こんなに柔らかいんだから」
肩には顎の感触。
タオル越しの背に鍛えられた筋肉を感じて、一護は盛大に固まった。
「うふふ、アタシがもっと大きくしてあげましょうか?」
その言葉に一護は意識を取り戻す。
浦原の視線は、タオルの巻かれた一護の胸元にある。
ついでに不埒な手が胸元に忍び寄ってきたから、一護は勢いよく打ち払った。
タコのようにへばり付く彼を引きはがすことは出来なかったが。
「離せよっ」
「嫌です」
ますます浦原は離れない。
それどころか自らの体を押しつけてくる浦原に赤面する一護だったが、許しておけるはずもない。
互いにタオル一枚。
けれど覆っていない部分の方が多くて、つまりそれだけ浦原とふれあう部分だって多い。
「ねえ、ついでにアタシのものになっちゃいましょうよ」
「何のついでだ!俺は俺のもんだよ!」
暴れている間に膝の上に乗せられる。
いくらか成長したとはいえ、背丈の差は30cm物差しがあっても足りないほど。
膝の上に居たところで、浦原の背を超すことはない。
「…んんっ」
覗き込むようにして、浦原が唇を重ねてくる。
抱き込まれた一護は逃げられなかった。
浦原の舌も、その腕も、一護を逃さない。
腹に回されていた手が徐々に上に滑っていった。
「…ぁッ」
巻いていたタオルはどこへ行ったのか。
そんなもの遠くに浮かんでいる。
いつの間に奪われたのか。
そんなこと浦原にとっては容易いことだ。
「や、」
「可愛い…一護さん」
まるで宝物のように一護の胸を包み込む大きな手。
浦原は耳をついばむ。
「うら…はら!」
逃げなければ。
逃がすまいと一護を囲う腕を振り切って。
「ねえ、気持ち良いでしょう?」
霞かかった一護の頭は、気持ちいいなんて答えははじき出さない。
ただ背筋がぞくぞくするという事実だけだ。
「…ん、あ」
「もっと啼いてくださいな」
「や、め…」
浦原の手は制止の声なんて聞かない。
小さくも大きくもない、けれど大きな手では包まれてしまう。
それに優しく触れられて、時にその頂に触れられて、一護は何度も身をよじった。
恥ずかしい。
こんなことをされている自分も、女みたいな声が響くこの場所も。
「恥ずかしくなんて無いですよ。何なら、恥ずかしいことしちゃいましょうか?」
ふれあう面積が多いから、心まで読まれてしまう。
耳の裏に口付けられる。ちゅ、っと吸われる。
胸に触れる手が、腹に下がる。
へそに下がって、下腹部に触れた。
「!」
その瞬間、一護は振り向かされた。
浦原の胸に強く顔を押しつけられる。
不埒な動きを止めたのは良いが、息苦しい。
数秒くらい、息が出来なかった。
まだ潜水をしていた方がマシだ、と朦朧とする意識で感じた。
「邪魔が入っちゃいましたねえ…どうしましょう」
邪魔?
力は幾分か緩められたものの、いまだ一護の体は浦原の上だ。
どうもこうもない。
さっさと離せ。
そう告げようとした一護は、力無く浦原にもたれかかった。
頭がぼうっとする。
「あれ、逆上せちゃったんスか」
浦原の心底残念そうな声を遠くに聞いて、一護の意識は途絶えた。
*
ゆっくり意識が上昇する。
一護は同じようにゆっくり目を開いた。
動けない。
目の前にあるのは何だ。
金色の髪と、少し長い睫。
うっすらと髭の生えた顎が、一護の顔にすり寄ってくる。
「〜〜!!」
思い出した。
眠る前に一護は風呂に入っていた。
そこで目の前の男に何をされたか、まで鮮明に思い出してしまった。
抱きすくめられて、タオルをはがされて、それで。
「オハヨウゴザイマス、一護さん」
顔を真っ赤に、それこそ耳たぶどころか首筋まで赤くした一護の唇に柔らかな感触。
かわいらしい音を立てて離れていくそれに、ついに一護の堪忍袋の緒は引きちぎられた。
「浦原ぁああ!!」
渾身の力で蹴り飛ばした。
ゲフッ、という声が聞こえたが、どうでも良い。
息を荒げた一護は蹲る男に詰め寄ろうとした。
そのとき、勢いよく襖が開く。
隊長副隊長勢揃い。
「一護ちゃんに何しとん!?」
「浦原隊長の不潔ー!」
「散れ、千本桜」
上からギン、雛森。
そしてこの場で斬魄刀を開放しだした白哉は流石に浮竹と京楽によって止められた。
「大丈夫かい?」
東仙に肩を触れられた一護は我に返って、自分の姿を見た。
浦原のことだ、服なんて適当に着せられているに違いないと思ったが、着物はきっちり着付けられていた。
もしかすると、このような事態になることを想定していたのか。
一護は安堵の息をついた。
しかし後日、浦原と一護がつきあっている、という噂が護廷を駆けめぐることになることに、この時の一護は気付いていなかった。