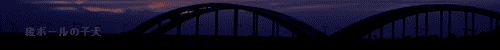
一護は幼い頃犬を飼っていた。
公園で捨てられていた子犬を拾ったのだ。
こっそり倉庫で飼っていた。
ある日一護が"れんむ"と名付けた犬と遊ぼうと倉庫へ行くと、犬はいなくなっていた。
病院では犬は飼えないからと、捨てられた。
数日後、犬の死骸を見た。
すでに原型なんて留めてはいなかったが、あれは確かに一護の犬だった。
あたりは騒然としていた。
そのざわめきの中、一護は一人隊長室にいた。
主はいない。
あるのは綺麗に折りたたまれた白い羽織と、その脇の一通の手紙。
一護が見た今まで一番綺麗な字で、"一護さんへ"と書かれた表書き。
「十二番隊副隊長、黒崎一護。浦原喜助の永久追放及び四楓院夜一による逃亡幇助の重要参考人として連行する」
相変わらず砕蜂の声には感情がない。
一護は振り返る。
その目に映すものなど何もない。
「従います」
ああ、彼女も捨てられてしまったのだ。
*
一護はすぐに釈放された。
その一件が一護とは無関係であることは明白であった。
同時に押収された手紙もまた、一護に当てられたものであるからと砕蜂はこっそり一護に返してくれた。
"あまり気を病まない方が良い"
一護と出会った人は皆そう言った。
夜一が去り、主がいなくなった四楓院家の屋敷で、一護は何一つする気が起こらなかった。
それに一護は養子入りしたとはいえ血族ではない。
当分こちらには戻ってこない旨を告げた。
行く当てのない一護を、白哉は後見人だからと引き取り、見た目の年頃の近いルキアがいることもあって、屋敷に住まわせるようにした。
もう一つ変わったことがある。
一護は浦原の跡を継いで、十二番隊の隊長となった。
技局は一護と無関係であったから、副局長であった涅マユリがその座に納まった。副隊長もまた、彼が再び就任した。
かつて浦原が纏っていた十二の文字が刻まれた羽織を身につけた一護は、骨を粉にするほど働いた。
その変貌ぶりには驚かれたが、仕方がないだろう、という同情の目が多かった。
夜一の腹心だった砕蜂も刑軍統括軍団長となり、二番隊の隊長と兼任していたが、あの日以来事務的なこと以外で喋ることはなかった。
慕っていたのだ。
夜一にも、浦原にも。
まるで姉や兄のように慕っていた人に裏切られた気がした。
「根を詰めるな」
うとうととしかけた一護の肩に、羽織が落とされる。
浮上した意識に一護がその人物の顔を見た。
「阿近さん」
「頑張るのが悪いとは言わないが、体をこわしては元も子もない。少し寝ろ」
「だけど…」
「四の五の言うな」
阿近は一護の肩を引き、自らの体に預けた。
一護も甘んじてそれを受け入れて、目を閉じる。
阿近の体は堅くて温かい。
*
既視感。
いや、この世界に一護はいたことがある。
死神になる前の話だ。
「黒崎隊長?」
「あ、ああ、何でもない」
一護は脇に控えた席官に呼びかけられ、意識を戻した。
見下ろす現世。
空座町と呼ばれるその街はかつて一護が生きていた頃に住んでいた町。
あれから一つも変わっていない。
1800 巨大虚数体が襲ってくる。
かつて浦原が発明した伝令神機にも似た機械は、数時間以内に現世へ現れる虚の姿を補足する。
通常虚圏に住まう虚達をどのように補足するのか、ましてや予測する事が出来るなど、一護にとっては想像も付かないことだが、この機械はそれを可能にした。
浦原が尸魂界を去ったことと同じくらい、この機械が尸魂界にもたらした影響は大きかった。
「良いか、もし周りに人間が居たら守れ。自分が出来る力でな。だけど危なくなったら逃げろ」
一護は部下から慕われていた。
死神としての実力もさることながら、もっとも一護が慕われる理由はその人柄が良さにあるだろう。
副官時代からそうであったが、隊長になってよりいっそうその傾向は強くなった。
一護が共にした席官は3人。
副隊長のマユリは今日も実験室に籠もりきりで、彼の卍解は周囲に被害をもたらすので彼は虚退治に向いていないから、不在だ。
1800まであと1分。
変わらない世界を見下ろしながら、一護はひっそり嘆息した。
「隊長ッ!」
突然沸いた虚の気配。
確かにこれは席官クラスでなければ手に負えない。
一護はざわついた背筋を放って、駆けだした。
虚は近い。
獣の叫び声。
一護は斬月を振り下ろした。
虚が歪み、離散した。
一筋縄ではいかなさそうだ。
背後では2匹の虚と退治する部下達の気配を感じる。
今度こそ逃がしはしない。
飛び上がった一護は虚がその姿を夕焼けに溶かす前に、仮面に叩き込んだ。
「…ぐっ…あ…」
消えた虚にため息をついた瞬間、肩に鋭い痛み。
身を引かせて一護はその方向を見やる。
「報告では3体のはずだったんだけどな」
血の滴る抉られた肩を押さえて、一護は目の前の虚達を見上げた。
そう、報告では、現れる虚は3体のはず。
今し方一護が殺した虚と、部下達が対峙している虚2体、うち一体もまた既に倒されている。
虚の群。
雑魚と呼ばれる虚だってその中に紛れてはいるけれど、数えれば両手では足りそうもない。
「これは救援、頼みたいぞ、流石に…」
呟いている合間にも、一護は虚を片づけていくが、埒があかない。
部下達はまだ残りの1匹を倒せていない。
ちょっと泣きたいかも。
その心情とは裏腹に、一護は気を引き締めて虚を片づけにかかる。
持久戦だ、霊圧を抑えられていたとしても倒せないことはない。
「な…っ」
一護が刀を構えなおしたと同時に、横を白い球状のものが通り抜けていく。
それも大量に。
球は虚へと向かい、虚を消し去っていく。
「無茶をしますねえ」
その声を聞いて、急に肩が痛み出した。
気が抜けたのかも知れない。
「…浦原、隊長…」
部下の一人の声。
一護はそれを背に聞きながら、目の前の男を見た。
その男も変わっていない。
変わったと言えば、死覇装と羽織が、センスの悪い帽子と作務衣と下駄に変わったぐらいだ。
「虚の群につっこんでいって死にかけたアナタを、お姫様だっこして助けたこと覚えてます?」
「ああ、あれは俺の一生の恥だ」
思い出したくもない過去だ。
「黒崎隊長ッ ご無事ですか」
虚を倒しおえた部下達が傍によってくる。
肩の傷を見て、息を飲んでいるようだ。
「無事だ。お前らも大丈夫そうな」
「はい。…… えっと…」
「ああ、そんな!アタシには見せないような笑顔を他の男なんかに!」
「五月蠅え!!」
浦原を気にしたそぶりを見せる部下を、一護は顔を緩ませることで下がらせた。
肝心の浦原は怒ったようで、人目を気にせず抱きついてきた彼の顔面を斬魄刀で殴りつける。
「触んな」
肩に触れようとした浦原の手をはたく。
一護はその後、浦原の背後にいた少女と少年、そして大男を見た。
見覚えがないものばかりだ。
「隊長」
「先に帰ってて良い。すぐ戻る」
「は…しかし……」
「俺はちょっとコイツに話がある。報告は俺がすますから、帰って休んで良いぞ」
渋々とした部下の気配が消えていくのを感じながら、一護は浦原を睨み付けた。
浦原は笑っている。
やっぱり帰れば良かった。
引きずられるようにして一護が連れてこられた一軒のぼろい家。
浦原商店、という看板が掲げられたそこはどうやら駄菓子屋さんのようだ(誰に売りつけるつもりか霊的商品も多くあった)。
「肩、痛むでしょう?治してあげますよ」
畳の敷かれた部屋に通されて、座らされた。
先ほどは払った手を甘んじて受け入れ、一護は目を閉じた。
「アタシが居なくて寂しかったでしょう?」
「夜一さんと離ればなれになったことは寂しかったけどな、お前は居なくなって清々したよ」
鬼道の苦手な一護と違って、浦原は鬼道が得意だった。
癒す力にさえ変えられる鬼道を肩に受けながら、一護は目を開く。
「変なことされてません?嫌なことされたら、すぐに顔面殴って逃げるんですよ」
「お前以上の変態は今のところ見たことねえなあ」
今も相変わらず、修兵はキスを迫ってくるし、白哉は結婚を迫ってくるが、浦原は知らなくて良いことだ。
知ったところでどうなるわけでもない。
それに彼らは浦原のように無理矢理押し倒して襲いかかってくるわけでもない。
「ねえ、今生の別れではありませんけど、次に会えるのは何百年後になるかも分からないでしょう?」
「そうだな。別に会えなくて良いけどな」
「だから抱かせて欲しい、って言ったら、アナタは"はい"って言ってくれます?」
肩に熱が籠もるのが分かった。
火照ったのは一護の体か、それとも浦原の霊気か。
「言わない」
「どうして?」
「俺は安くないからな。って、顔近づけるな!」
近づいてくる浦原の顔を、一護は両手で押しのけた。
とたんバランスが崩れて、視界も回った。
「大人しくなさい」
一護の体は突然動かなくなった。
縛道を掛けられた、と思っても振りほどけない。
詠唱破棄どころか、何であるかすら唱えていない。
たとえその番数が低くとも、自分よりも勝る相手の縛道は解けないのだ。
(嘘だろー!?)
「夢にも見たアナタの純潔を手に入れられるなんて、今日は素晴らしい日ですね」
声の出せない一護を知ってか知らずか、浦原はうっそりと笑った。
正直不気味だと感じたが、今はそんなことよりこの不穏な空気と体制をどうにかしなければ、と思った。
乾いた唇が触れる。
浦原にはもう数え切れないほど襲われたけれど、キスだって何度されたか分からない。
その時、どんなに一護が嫌がっても、逃げ切れたことなんて一度もなかった。
「アナタは信じられないって言うんでしょうけど、一目惚れなんですよ」
そうだ、信じられない。
この男は始め酷く冷たくて、けれどそれが演技であったことは知ったけれど、情愛を抱いていたなんて思えない。
愛を告げる俗な言葉さえ告げなかった。
告げたところで一護は受け入れるつもりも、流されるつもりもなかったが、もしかしたら何かが変わったかも知れない。
「本当はあちらでずっと守っていこうと思っていたんです」
差し入れられる舌から逃げられない。
一護は何度も顔を振ろうとした。
上あごを舐められて、涙をこぼした。
「でもそれが適わなくなった。アナタを連れて行かなかったことを何度後悔したと思います?」
涙を掬い上げられる。
冷たい唇と違って、その舌は酷く熱を帯びていた。
一護は手を振り上げた。
その手のひらは浦原の頬を打つ。
「五月蠅えよ!俺は清々してるって言っただろ!」
縛道が解けたのだ。
いや、解けたのではない。
浦原が解いた。
組み敷かれたまま、一護は浦原を見上げた。
打たれた頬を手でかばうこともせずに、浦原は一護を見下ろした。
「あんたが居なって俺は隊長だ。おかげで守れるものも増えた。居なくなって感謝してるぐらいだっ」
「ええ、彼らはよくアナタを慕っていました。アタシなんかより素晴らしい上司でしょうね」
そうだ、浦原は上司としてはあまり良い、と呼べる男ではなかった。
過保護なのには一護に対してだけで、他の部下には非情だった。
そんなところがあまり好きではなかった。
「でもアタシは後悔したんです。殺されても良い、アナタを連れ去ろうと何度もあちらに行こうと思った」
浦原の細い堅い指が頬に触れる。
慈しむようなその仕草に、一護は頭に血を上らせた。
「後悔するぐらいなら!始めから捨てなきゃ良かっただろ!」
一護は死んだ犬の姿を見たとき、後悔した。
犬は人から餌を与えられる、と言うことを知って、自ら餌をとることが出来なくなった。
「捨てるぐらいなら、拾わなきゃ良かったんだッ」
拾わなければ良かった、と後悔した。
涙が指先をぬらした。
「ここに留まる気はありませんか?」
「ない。戻る、って約束したし」
迎えも来た。
一護は声に出さなかったけれど、浦原は一護の上から体を除けた。
最後に、と合わされた唇に一護も抵抗はしない。
「兄は愚かだ」
「朽木さんに言われなくたって、十分わかっていますよ」
「一護、そなたの部下達が"浦原喜助に連れ去られた"、と報告してきた。後でよく謝っておけ」
「あー…うん」
連れ去られたわけではなかったけれど。
白哉は至極真面目な顔だ。
本当に彼らはそう報告したのだろう。一護は良い上司だが、よく無茶をして部下を心配させる。
「帰るぞ。一護」
尸魂界への門が開く。
そこへ先にくぐった白哉の後を追って、一護も足を踏み入れる。
「また会いに来てください」
「誰が行くか」
浦原は手を伸ばしたけれど、弾かれてしまった。
もう二度と彼は尸魂界に足を踏み入れることは出来ないのだ。
一護が現世に降りてこない限り、浦原は一護の声を聞くことさえ適わない。
「今度こそ一護さんの純潔奪って差し上げます」
浦原は笑って言った。
振り返った一護は、いつものように眉間に皺を寄せた。
「死ね。三回くらい死ね」
「つれないッ!」