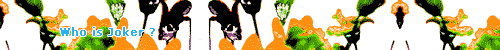
西暦20XX年。
日本はいまだ、1990年代のバブル崩壊の影響から回復出来ずにいた。
「… またか」
警視庁刑事部捜査一課・特殊犯捜査第4係。
そこに設置された捜査本部で、一護は一つの小包と睨めっこをしていた。
今だ未開封の小包、と呼ぶには少しばかり大きな箱。
これが爆弾でないことは既に確認済み。
送り主は紅姫。
モノクルで隠す顔は常に変わるがその全てが秀麗。
その容姿ゆえに、界隈を賑わす怪盗、と言う名の泥棒だ。
しかし通り名が紅姫と言っても、その怪盗は女ではない。
本名も分かっている。
「毎回、毎回、浦原の奴…っ」
一護はつけていた手袋を外し、指先を小箱に触れた。
指紋照合型のロックは、一護の指先でないと解除できない。
ピピッと電子音。
カパッと開いた箱の中身は、小さなカードと、
「毎回、熱烈なことで」
真っ赤な薔薇の花束。
その薔薇にも負けぬほどの赤い髪をなびかせて、同僚の恋次はその花束を取った。
「で、今回の贈り物は指輪か。これは本気だな」
「おーい。花太郎!これ、鑑識に回してくれ」
「分かりましたー」
「お前に掛かれば天下の怪盗も形無しだぜ」
一護は手袋をはめ直して、銀色の指輪がはまったジュエリーケースをつかみ上げる。
転売しても二束三文だろうが、高そうだ。
それにきっと足は掴めないだろう。
「今日も明日も明後日も残業か…」
そう漏らして肩を落とした。
犯行予告時間は、明後日の22:00。
空座町博物館に飾られている、「アンドロメダ」を盗みにくる、とご丁寧に書いてある。
これから本部長である白哉と、補佐である一護は紅姫確保の為にありとあらゆる策を練らなければならないのだ。
*
けたたましいサイレン。
真夜中なのに近所迷惑なライトがたかれる。
「…眠い…」
夜更かしは肌の敵だ。
ろくな手入れをしていないが、「赤ちゃん肌だもち肌だ」、と特殊犯捜査第1係の乱菊絶賛の肌を持つ一護は、上司にそう叫びたかった。
「モタモタしてっと、誘拐されるぞ」
「されねえよ!」
「この前痴漢にあったくせして…グハッ」
以前の張り込みで、痴漢にあったことを思い出した一護は、思い出す原因となった男の腹を蹴った。
もちろん、そのときの痴漢も一護直々に伸してやった。
「大体!だからお前がここに居るんだろ!室内なのに!」
「そう、前回は警官から痴漢行為に遭い、未だに高校生に間違われるほど、うら若き乙女でいらっしゃる黒崎一護さんを守れっていう上司の命令でね」
白哉が心配して、今度は恋次を同行させているのだ。
戦力を集中させるのは愚策だ、と進言したが却下されてしまった。
「俺は25だ!」
25にはとうてい思えない童顔を歪めて、吐き捨てた。
それと同時になるのは、空座町にある古時計。
時は22時。
瞬間、辺りが暗転。
「照明班!明かりを復旧しろ!」
白哉の声が飛ぶ。
何者か、もちろんくだんの怪盗に決まっている、によって落とされた電源はすぐに復活した。
月明かりに負けないほどの明かりに、黒い陰。
宙に浮き、黒い外套をはためかせるは一人の美丈夫。
「お久しぶりです。朽木さん。アナタも寂しかったんじゃないですか?」
音符マーク(♪)が付きそうな、軽快な声は機械を通して伝わる。
「心配はいらぬ。これから毎日嫌と言うほど顔を合わせてやるのだからな」
「冗談キツいっス。でもアタシの一護さんなら話は別ですよ」
そういえばいらっしゃいませんね、と心底残念そうな声。
白哉は、顔も見えぬほど遠い男を睨んだ。
「一護」
視線はそらさぬまま、襟元の無線機に向かって一言。
「よお、浦原。久しぶりだなあ。会いたかったぜ」
「嬉しい言葉ですこと」
窓枠に堅い音。
「それなら、アタシと付き合ってください」
「刑務所までなら喜んで付き合ってやる」
そのまま土の付いた革靴で赤い絨毯に降り立った浦原は、モノクル越しに笑う。
今日の顔もまた、以前のものとは違う。
けれど、どの顔も美しかった。
「相変わらずつれない人だ。そうそう、今日のテーマはペルセウスでしてね」
化け鯨の生け贄になりかけたアンドロメダを救った英雄だ。
「どうでも良い」
放っていたらベラベラ喋り続けそうな浦原に向かって突き出すのは、一護の細く白い指。
それは確保の合図だ。
場にいた警官は浦原確保に動く。
それに困ったように笑った浦原は、小さな卓球のボールのようなものを投げた。
地面に跳ねると同時に目映い光が一室を満たす。
「毎回同じパターンはちょっと飽きてきました」
「今日ばかりは飽きないぜ?」
絵画に触れた、その手から金属音。
ありゃ、という間抜けな声の主は、それに繋がる手を見た。
「恋次!」
「任せろ」
一護の髪に負けない派手な髪の男とその部下がドアを蹴破るようにして入ってきた。
浦原の身体を完全に拘束するために。
完全なる勝利。
「それは困ります」
に成るはずだった。
「ッ 吸うな!!」
「んな無茶な!」
一護と恋次の漫才のようなやり取りの最中も、一室を煙が満たす。
大きな体躯の男達が、次々に倒れ込んだ。
恋次も例外ではない。
「ま、こんなもんでしょ」
浦原は、部屋中に転がる眠り転けた男達を、よいしょと時には蹴りながら合間を縫って窓へと向かう。
入ってきたときのように、窓枠に足をかけて、足下に居る白哉を見下ろした。
「じゃ、朽木さん。また会いましょ」
取り出したのは、怪盗おきまりのアドバルーン。
どういうからくりか、人一人乗せても空を飛ぶし、操縦も効いた。
「そうそう。これ、贋作みたいっスね。要らないんで、お返ししますよ」
5階分の高さから投げ落とすのは、先に手に入れたはずの絵画だ。
足下でギャーだのワーだの逃げろだのの声を聞いて、浦原は窓枠を蹴った。
「代わりと言っては贅沢ですけど、一護さん、貰っていきますから」
*
浦原を捕まえたらおめでとうパーティ。
逃げられたら残念パーティ。
今のところ開催されたのは残念パーティのみ。
白哉の無言の説教(と呼べるのかは甚だ疑問だが)で始まり、やけ酒に終わる。
「…一護さん」
俺、酒に強くねえからすぐに酔うんだよな。
「一護さん、ってば」
あー五月蠅い。
大体飲ましたのはお前だろうが、恋次。
「起きないならキスしちゃいますよ」
巫山戯るなよ白哉。
上司の癖してセクハラまがいのことばっかりしやがって。
「あんなことやこんなこともしちゃいますからねー」
それから唇に冷たい感触。
一護は、あまりのくすぐったさに目を覚ました。
「ああもう!お前、今日こそ豚小屋にぶち込んでやる!」
琥珀の目をカッと見開いて、一護は目の前の男に叫んだ。
…白哉でも、恋次でもない。
親しいどころか、ましては見覚えのある顔ではなかった。
「……誰だ、てめえ…」
枯草色の髪に、緑翠の瞳。
あ、これは白哉に負けない男前だ、と一護は眉を寄せながらも思った。
「アタシですよ、一護さん」
「う、浦原ッ?!」
声、にも聞き覚えがない。
あの怪盗はいつも頓珍漢としか思えない声音を使っている。
よく警察24時で一般人に使っているモザイクの声のような。
けれどその独特なしゃべり方をする人間を、一護は一人しか知らない。
「お前それ…って何だこれっ!?」
作り物なら引っぺがそうと伸ばした手、片手を伸ばしたつもりなのに両手。
細い手首には銀色の輪っか。
ある世界ではワッパと呼ばれて恐れられる、警察の必須アイテムだ。
「一護さんの手錠です。ちょっとお借りしましたよん」
いつもながら巫山戯た口調だ。
罵声を上げようと開いた口を、何かで塞がれる。
「っんん…!」
ついでに、口が開いていたものだから、何かが入ってくる。
妙に熱くて濡れた。
「…っふぁ…ん…」
それが口づけされているのだと、舌なのだと理解した脳はあまりのことに静止した。
「アンドロメダは偽物でしたけど、アタシにとっては一護さんが至宝ですよ」
思い出した!
浦原に手錠をかけ、恋次が部屋に入ってきて、煙。
それからの記憶がない。
あの煙は催眠効果を持っていて、うっかり吸い込んだ一護は、どういう訳か連行されたのだ。
恋次に「誘拐されるなよ」と言われたが、これは洒落にならない。
しかもベッドと思わしき場所に押し倒されている。状況は最悪。
「というわけで、一護さんと素敵な夜を過ごすためにとあるスイートルームを借りちゃいました。ベッドもキングサイズです」
浦原の指先が一護の濡れた唇をなぞる。
それで先ほど何をされたのか思い出した一護は、顔を真っ赤に染めて声を張り上げる。
「てめっ!罪状を増やす気かッ!」
恋人でもない(第一合意の上ではない)一護にキスするなんて、強制わいせつ罪だ。
窃盗罪に、器物破損・公共物破損、公務執行妨害という前科持ちの浦原を睨み付ける。
「どうせ捕まる気なんてありませんしねえ。ここで婦女暴行罪を付け加えても結構ですよ」
「勘弁してくれっ!」
顔を近づけてくる浦原を、手錠で拘束された手で、押し返す。
さらりと、強姦しちゃうぞと言ってのけた男を近づけてはたまらない。
「どうして?」
「どうして、って。そういう仲じゃないだろ。ましてはお前は怪盗で、おれは刑事だ!」
浦原はその秀麗な眉を下げた。
困った表情の浦原は何度も見てきたが、これほどまでに情けない顔は見たことがない。
第一。
「これ、本物なのか?」
「ええ。素顔ですよ。本邦初公開です」
「あー…特殊写真係に行かなきゃな」
それでモンタージュ写真を。
一護は必死に浦原の顔を見た、いや見つめた。
「やだ一護さんってば。アタシが男前だからって」
「水たまりに溺れて死ね」
熱心に見つめてくる一護に何を刺激されたのか、また浦原は顔を近づけてくる。
「アタシがどういう覚悟で、ここに連れてきたか分かります?」
分からない。
むしろ分かりたくもない。
だが素直な一護は素直に頭を振った。
「アナタが好きです。もし怪盗でなければ、アナタはアタシを好きになってくれました?」
あり得ない話だ。
一護は首を振った。
「もし」の話をされても分からない。
「それが、お前の覚悟と何の関係があるんだ」
「アナタを殺す覚悟。素顔を見られたからには、生かしておけない、てよく言うでしょう?」
振った首に、手をかけられる。
息苦しい。
力を込められて、一護はその分手錠をかけられた手で懸命にのしかかる男の身体を押した。
「手に入らないものはね、壊してしまう主義なんです」
手際よく気道が潰されていく。
目尻に涙を浮かべ、藻掻いた。
藻掻く手に力が入らなくなっても。
「なーんて、本気にしました?」
急に入ってきた空気のかたまりに、一護は盛大に咳き込んだ。
身を屈ませ、目尻に浮かんだ涙がこぼれる。
「う、ら…ってめっ…」
殺人未遂罪も追加だコラ!
と一護は叫びたかったが、どだい無理だった。
「あ、でも一護さんを好きなのは本気です。ねね、ついでだから子供も作りましょうよ」
「何がついでだ! てか、どこ触ってんだ!つめた…っ」
「お肌すべすべ」
ひんやりとした手が腹部に触れる。
カッターシャツの合間から手が滑り込んでいた。
冷たさに鳥肌を立てた一護は、足蹴りを食らわす。
「足癖の悪い子。縛られたいんですか?」
一度懇親の蹴りを腹に食らっておきながら、平気な顔をしている浦原は、その足をとった。
折り曲げられて、足を割られる。
「止めろっ変態!」
「どうせアタシは変態です」
服に入った手が上に進み、下着に触れる。
これは変態どころの話ではない。
ああ何で今日に限ってフロントフックをつけてきたんだとか、何でそんなに手際が良いんだとか、いい加減手錠を外して欲しい、とか。
言いたいことはたくさんあった。
「やめ…っ」
フックが外れる。
解放された膨らみを冷たい手に包まれて、一護は頭を振った。
その頭すら口づけで固定される。
「は…、や…あっ」
「子供が出来たら、そうですね。何処かの国でひっそりと暮らしましょうか」
唇を離し、一時的に抵抗する力さえ奪った浦原は、一護を見下ろして微笑んだ。
「そうしたら一護さんも辞職ですか。残念だなあ。ミニスカポリスな一護さんが見られなくなるなんて」
「そもそも制服なんか着てねえよっ!」
「あら。前は着ていらしたでしょ?」
以前この男が言っていたが、交通課にいたときの婦人警官姿の一護を見て、一目惚れした、らしい。
やはり変態だ。
とにかくどうにかしなければ、と一護は再び手で浦原の胸を押す。
「お行儀の悪い手だ」
一護の頬に添えられていた手で、頭上にひとまとめ。
元々手錠で拘束されているのだから、それは容易いはずだ。
ベルトを外され、ズボンを引き抜かれた。
「お前!自分が何やってんのか、わかってんのかっ?!」
震える身体を叱咤して、一護は怒鳴った。
浦原は一瞬だけ面食らった表情をすぐに引っ込めると、頬に顔を寄せる。
「分かっています。アタシはもとより犯罪者だ。今更罪状が増えても気にしません」
「ッ」
「そうだ。取引をしましょ。一護さん」
息を吹きかけられ、耳を囓られた。
顔を赤らめ目を見開いた一護に、浦原が笑う。
「一、ここでアナタを犯します。その代わりアタシは警察に出頭しましょう」
「二、今日はここで諦めます。だから、アナタも今日の所はアタシを見逃してください」
さあ、どうします?
一護は開閉しそうな口を、つぐんで食いしばった。
「……っ」
どちらも困る。
「……… 残念。時間切れのようです」
その瞬間身が軽くなった。
そして数瞬にドアが乱暴に蹴破られる。
「そこまでだっ!紅姫、いや浦原喜助!」
白哉の声だ。
「部下に発信器をつけるなんてどういう神経してるんでしょ。途中で気づいて壊したのに、わざわざ場所を割り出すとはね」
「女を手込めにしようとする貴様に言われたくなどない」
「失礼っスよ。アタシは一護さんにしか興味ないんですから」
解放された窓枠に立つ男の顔は、ペルセウスと名乗ったときと同じだ。
先までの顔とは違う。
「ではまた。お会いしましょう」
浦原が背を向けた瞬間。
「蜂巣にして構わん」
「びゃく…っ」
「撃てッ!」
銃を構えていた警官達の一斉掃銃。
一護の制止の声も上げられぬまま。
それから数秒で銃声が鳴り終わる。
そこにはきっと原型も分からぬほど血まみれになった男が倒れているのだろう。
立ちこめた硝煙が消えていく。
一護は身を起こし、窓側に走り寄った。
穴だらけの、窓。ガラスはもう砕け散っている。
「浦原…っ」
「お呼びですか?」
もしかしたら地上に落ちたのかも。
そう思って目もくらむ高さの下を見下ろした一護は、声に顔を上げた。
「今度会うときは、アナタとは怪盗と警官でなければ宜しいですね」
宙に浮かぶ浦原は一護に微笑みかけて、すぐに消えた。
「一護。大丈夫か?」
しばらく呆然としていた一護の肩に、高そうな生地で出来たコートが被せられる。
男物の大きなそれは、太ももの際どい位置にあるシャツとは違って、十分に膝まで覆う。
それから腕を取られ、手錠が外された。
そこでようやく気づいた。
「う、わぁっ」
上はカッターシャツ一枚、だが下着は外れている。
下は下着一枚、もちろんズボンはそこのベッドに放り投げられたまま。
「一護。浦原の素顔は見たか?」
顔を赤らめて借りたコートをたぐり寄せた一護は、覗き込んでくる白哉の顔を見て、息を飲む。
刑事の顔だ。
「…… いや」
「そうか…」
相変わらず無表情だが残念そうな色を浮かべている。
何処にも一護を訝しむ色なんてない。
「引き上げるぞ。一護も着替えを済ませたら降りてくると良い」
「お前も出て行けッ!」
撤収していく恋次や他の警官達に混じって白哉も出て行くか、と思いきやこちらを見やったまま。
怒鳴った一護にようやく出て行った。
「くそ…っ 浦原の野郎…」
極度の緊張から解放され、へたり込んだ一護は、そこでようやく自分の右手の薬指に輝くものを見つけた。
*
バルーンをたたみ込む。
演出上利便性が高いとはいえ悪目立ちするのだ。
「取引、ねえ」
自らが一護に持ちかけた、取引。
それは公平ではない。
守るという確約はないし、はっきり言ってどちらの条件も一護には不利だ。
「優しい人」
それでも一護は必死で考えた。
一護は自らの手で浦原を捕らえたいと思っていたし、そのために身体を差し出すなんてあり得ない。
けれど浦原を捕らえられるのか、という保証はない。
一護が望めば。
いくらでも繋がってみせるのに。
一護という名の檻になら、いくらでもいつまでも囚われたって良い。