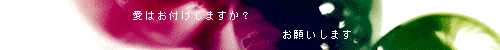
Not in
Employment,
Education or
Training
NEET。
中学、高校と進学校へ通い、大学は天下のT大を合格、それなりに通って留年することなく卒業、それで終わり。
働きたくもなければバイトもしたくない。大学院に進むなんて以ての外。
そうこうしているうちに10年と少し経って、今はもう34歳。
来年35歳を迎えようとしている浦原は、あと1年というニートの時を満喫していた。
金には困らない。
親のすねをガジガジしている。
今世の風潮にのってのって乗りまくっている。
けれどパラサイトシングルではない。
シングルはあるけれど、まあ広義パラサイト:寄生ではあるが親と同居はしていない。
今日の夕ご飯もカップ麺。
いつも通りの下らない日常が終わろうとしていた。
「以上、計5点で、1350円です」
1,000円札と500円玉を出す。
おつりは150円か、自動販売機でペットボトルが一本買えるな、なんて効率の悪いことを考えた。
聞いたことのない、女(というには若いか)の声だ。
以前バイト募集の張り紙をしていたから、誰かが採用されたのだろう。
「150円のお返しです」
そのチェーン展開をするコンビニの制服を着た少女は、差し支えのない営業用スマイルを浮かべていた。
橙色の髪。
よくもまあ面接に通ったものだ、といつもの浦原ならそう思ったけれど。
(…可愛い)
おつりを受け取るはずの手がぶれて、100円玉一枚と50円玉一枚が、レジテーブルに転がった。
「申し訳ございません」
明らかな浦原の過失であるが、接客業はそうも言っていられない。
少女はレジから新しいお金を出すと、もう一度浦原の手に小銭を乗せた。
そのとき柔らかな手が触れて、年甲斐もなく心臓が跳ねた。
「有難うございました、またのお越しをお待ちしております」
ずいぶんとぎこちない動きだった、はずだ。
ゼンマイ仕掛けのブリキのように浦原はコンビニの自動ドアをくぐった。
ていうか、いつものエロ雑誌なんて買わなければ良かった!
*
あの少女の名前は黒崎一護というらしい(名札を見た)
空座第一高校に通う高校1年生(橙の髪というのはあまりに特徴的で、調べればすぐに分かった)
ということはまだ、15か16。
若い。いや、幼い。
「…可愛かったな…一護さん…」
こっそり名前呼び。
だが正々堂々名前呼びをするような関係になりたい!
つまりは、懇ろな関係に!
が、相手は高校生。
一回りどころか、約20も違うし、下手すれば淫行罪で捕まる。
一護のシフトは、月木土の18:00〜22:00。
今まで気の向くままにコンビニを向かっていた浦原は、その時間に足を運んだ。
もちろんレジは一護の所のみだ。
今日で20回目。
いい加減顔は覚えて貰っているだろうか。
「いらっしゃいませー」
すでに習慣付いた橙の頭を探す。
レジには居ない。
商品充填だろうかと思い、商品棚に目を配る。
居ない。
奥の倉庫にでも居るのだろうかと思い、10分ほど漫画雑誌(愛読の成人向け雑誌はもしも一護が現れたときのために読まない)を読みながら、ちらちらと倉庫に目を向ける。
いっこうに出てくる気配は無かった。
「あの…つかぬ事をお伺いしますけど」
金額を告げられる前に、レジスターに表示された金額分きっちりと出した浦原は、目の前の白い髪の男に声を掛けた。
「橙色の髪の子、今日は居ないんすか?」
「黒崎くんなら今テスト週間中だが…」
「そう、っすか…」
浦原はがっくりと肩を落とす。
レシートは要らないと告げて、店を出た。
「店長、何ですかアレ」
「さあ?隠れファンって奴じゃないのか?黒崎は可愛いし」
「そういえば最近見ますね」
いつも一護の相方である海燕は、度々あの男の姿を目撃している。ここ最近。
顔見知りとはとうてい思えない。
それに店長である浮竹とあまり年は変わらなさそうだ。
「まさか…ストーカー?」
「それはいかんな!黒崎に気をつけるよう言っておこう」
*
一護がバイトに戻ってきた。
浦原もその日から欠かさず通い続けている。
何だか相方の男の視線が厳しい気がするが、きっと気のせいだろう。
一護は今商品の充填中だ。
「何かおすすめの商品ってありますか?」
「え?」
心臓が口から飛び出そうだ。
その位緊張した。
おにぎりを並べていた一護の手が止まり、頭一つ分高い浦原の顔を見上げた。
「いや、最近新商品多いでしょ。手当たり次第よりも店員さんの話聞く方が良いかなって…」
もしかしたら自分の顔は赤いかも知れない。
そう思いながら浦原は、まじまじと一護の顔を見た。
「ああ。……だったら、このスープスパはどうですか? ええっと、よくこってりしたものを買ってるし…」
覚えてくれていた!
天にも昇るような思いだ。
迷わず陳列されたスープスパ、ことホワイトソースベースのスープスパゲティを取る。
「買います。あ、アタシの名前、浦原喜助って言うんですけど」
一護の顔は、はあ、それが?といったそれだ。
大体そのオカマ語はなんだ、とも伝わってくる。
「早速で悪いんですけど、好きです。お付き合いしてください」
「お断りします」
一国玉砕だ。
神風特攻隊はもっと鮮やかに散ったに違いない。
「一護、レジ頼むー」
「はーい」
夕方まばらとはいえ一人で回すには厳しい店内に、一護は早々に補充用の棚を倉庫に直すとレジへと戻った。
後には石像のように固まる浦原が残るだけだ。
「420円のお買いあげです。ちょうどお預かりします。有難うございました。またのお越しお待ちしております」
何とかして復活した浦原の会計を済ませた一護は、また商品補充に戻っていった。
*
ショックだ。
ショックすぎる。
あれからどうやって家に戻ったのか記憶にない。
次の日、浦原は近所の本屋に出向いた。
一護と出会ってから絶っていた成人向け雑誌を買おうと思って、そのコーナーに出向く。
めぼしい、というよりいつも購読している成人向け雑誌を手に取った。
表紙は名前の知らないグラビアモデル、最近人気が出てきたらしいが興味がなかった。
それを手にしてレジへと向かう最中。
鮮やかな橙に目を奪われた。
「あ」
レジの少し手前。
一護も浦原に気づいて顔を上げた。
腕には参考書と思わしき本とファッション雑誌、そして一冊の少年漫画、意外だ。
「知り合いか?」
「俺のバイト先に来る、客」
「ああ。海燕殿の言っていたストーカーか」
一護よりも少し背の低い黒髪の少女が一護を見ている。
一人称「俺」なんだ、なんて感心している場合ではない。
「こ、恋人候補ですよう」
慌てて訂正した浦原は、少女等から冷たい視線を向けられていることに気づいた。
矛先はその手の中の、成人向け雑誌。ついでに浦原。
「そういえばチャッピーのCD、もう出てるんじゃないのか?今日、火曜だし」
「おお!そうであったな!あとでCDコーナーにも寄ってくれ」
「りょーかい」
はやりのロックバンド、チャッピーのコアファンであるルキアは目を輝かせた。
そのルキアと、あっさり無視した一護はレジで会計を済ませた。
「ちょっ、ちょっと待ってください!一護さん!」
CDコーナーへ消えていく一護を、きっちり金を払った浦原は追った。
「あーウゼえ。そもそも馴れ馴れしく人の名前呼ぶんじゃねえよ」
いつものコンビニでの丁寧な言葉遣いが嘘のようだ。
が、この口調は一護らしくて良い。
可愛らしい顔とのギャップが最高だ。
そんなことを考えているとは露知らず、一護は勘定をしているルキアの横で、しつこい男を一喝した。
「あ、だったらアタシも喜助、呼びで構いませんから」
「お呼びじゃねえ。大体、なんでこんな真っ昼間っからウロウロしてんだ」
今は14:00。
一護の学校は珍しく早く終わったが、きっと浦原はそうではないはずだ。
どうみても学生には見えない、という視線を受けた。
「だって仕事してませんもん」
流行のニートです、というのは憚れたが隠してはおけない。
いずれ懇ろになる仲なのだ(あくまでも浦原にとっての予定)
「でも将来の職業は、一護さんのお婿さんですかね」
「お、ルキア終わったのか。帰ろうぜ」
CDの入った小袋を大事そうに抱えたルキアと一護は店を出ていった。
ルキアは自転車に乗ろうとし、一護は歩いていることから、おそらく一護の家はこの近くなのだ。
バイト先のコンビニも近い。
本屋の無駄に広い駐車場で、浦原は自動車の鍵をちらつかせながらこう言った。
「ねえねえ。一護さん。その参考書重いでしょ?送っていきますよ」
「不審者そのものだな」
冷ややかなルキア、と呼ばれた少女の視線を頂く。
「エロ本買うような男に付いていくな、って言われてんだ」
「何ですって!エロ本を買わない男なんて居ません。そんな奴が居るなら、男として終わってます!」
「お前は人間として終わってる」
一度もこちらを見ようとしない一護の腕を掴んだ。
否応なしに一護は立ち止まるざるをえない。
「すみませーん。ここに痴漢がいますー」
「ちょっ 冗談!」
「だったら離せっ、よっ」
「部屋に連れ込むとか、車の中で押し倒すとかしません!無傷でおうちまで送りますから!ね、ね!?」
「不審者は大抵そう言うんだ」
腕をブンブン振った一護の腕は意地でも放さない。
片手に荷物を抱えているからか、抵抗が少ない。
不愉快そうに浦原を一瞥、いや睨み付けてくる。
「ていうかさ、俺、アンタのこと何も知らないわけよ」
困ったときはどうも、唇をとがらす癖があるらしい。
浦原はキスしたい、と思ったが実行に移せば確実に警察行きだ。
「だったらお話ししましょう。ね?だから…」
「あーっ五月蠅い!分かった、分かったから手離せ。痛いんだよ」
すぐに手を離した。
力を無意識とはいえ込めていたせいか、赤くなってしまった。
ごめんなさい、と告げると一護はまた口をとがらせ眉間に皺を寄せた。
「ルキア。コイツしつこいし、ちょっと付き合ってくるから、俺が帰らない、って電話がきたら警察に通報してくれ」
「お、おい!一護」
「平気だって。俺を誰だと思ってるんだよ」
「…空手でインターハイ、3位入賞者様です」
そうなんだよな、竜貴も勝てなかったあのゴリラに負けたわけだよ、と一護は呟く。
インターハイ。
全国高等学校総合体育大会で3位入賞。
浦原の背筋は凍り付いた。