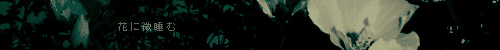
2.5 小さなラプンツェル
花太郎という名前は、覚えやすいと言われる。
良い名前だと。
けれど、男なのに『はな』だなんて、元々頑強な体つきでもないから、まるで女のようだ。
はな、と。
拙い口調で呼ぶ声がなければ、きっと嫌いになっていた。
「はな」
三日後に祝言を控えた一護は、衣装合わせでてんてこ舞い。
美しい絹で出来た白い小袖を纏って、花太郎へ笑みを向ける。
「どうだ。似合うか?」
一護に引っ張られるようにして、私室に招き入れられた。
結婚前に、他の男へその神聖なる姿を見せるなんて。
婚約者に知られたら、多分首と胴体は繋がっていまい。
「良く似合ってますよ」
一護を着せ替え人形のようにしていた女中は、御簾の外。
けれど耳を立ててこちらを伺う。
「良いのか?」
「何がですか?」
しずしずと歩み寄っていた一護は、今花太郎の目の前だ。
小柄な自分でも見下ろせる、まだ幼い少女は、三日後男の元へ嫁ぐという。
「俺に付いてきて、いいのか?」
一護が生まれてから今まで付き従ってきた。
乳母子という絆で、一護は花太郎を縛るから。
ようやくその鎖が解かれようとしている。
「良いんです。僕の幸せは、一護さんの幸せですから」
その鎖を再び巻き付けたのは花太郎自身。
そうか、と何処か嬉しそうに微笑む一護を見るのが、花太郎の幸せだった。
*
柔らかな、人のものとは思えないような。
その小さな手を取ったのは、今思えば運命としか思えない。
「黒崎一護様。そなたは一生をかけて、この方にお仕えするのだ」
厳格であった花太郎の母が、そう告げる。
生まれてからすぐに、実母から引き離された。
一護の母が王家の出身でありながら、中流貴族に過ぎぬ男と駆け落ちしたせいだ。
既に一護を身ごもっていた彼女は王鍵で閉じられた世界へ引き戻されることはなく、その自由の代わりに一護を奪い取られた。
可哀想な、子供。
パッチリと開いた琥珀が、花太郎を捕らえる。
「初めまして。一護様。山田花太郎と申します」
赤子に告げても分からぬ言葉を。
それでも儀礼のように、花太郎は紡いだ。
はな、と。
何の言葉よりも早く、この幼子に自身の名を呼ばれることを、花太郎は知らない。