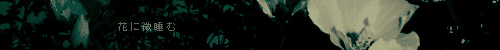
2. 利己的遺伝子
『命に代えてもお守りします』
そう誓い、それでも足りぬ、との言葉を頂いて。
最年少入学を果たし、異例の入学時からの飛び級、5回生として特進クラスへ入学された。
愛しい乳母子のために、花太郎は二回目の統学院学生生活を体験中。
流魂街出身の男達に慕われる右の、雛森。
瀞霊廷生まれの生粋の貴族達に好まれる左の、黒崎。
と、特進クラス二大高嶺の花となった一護は、今、同級生の男に囲まれて、秀麗な眉を下げている。
あちらこちらから投げかけられる問いに困惑中。
「ええ、と?」
次の休みは是非我が家に、と宣う何処かの御貴族様。
休みになれば、一護は婚約者様のお家へ招かれることは露ほども知らない。
幾分か高い彼らの波をかき分けて、ようやく辿り着く深窓の花。
「花太郎」
「次は鬼道の授業ですよ」
誰もが羨む。その手を引く権利をこの中で唯一持ち得ている花太郎は、幼い頃そうしていたように一護の手を引いた。
途中刺すような視線を頂くけれど、かの婚約者様に比べればこんなもの。
「一護くん!」
波をかき分けようやく脱出した先に、黒髪の少女。
雛森桃、一護と人気を二分する、人当たりの良い少女は背伸びして、その手を振る。
「桃さん。どうかした?」
あまり花太郎と背丈の変わらぬ雛森は、それでも一護よりはまだ少し背が高い。
一護は雛森を少し見上げて、首をかしげた。
端から見れば両手に花。
けれど雛森の後ろには、親衛隊と称される赤髪と、金髪の青年。
彼女にはきっとそんな気はないのだろうが。
「私たちも一緒に行っても良い?」
その問いに一護は花太郎を見上げる。
一護自身は構わないと、いうのだろう。
「僕は構いません。是非、一緒に」
「…だって」
そう言って一護は自分の机に戻り、教本を取り出す。
中級鬼道の手引きを書いたそれは、まだ新品同様。
「そういえば、来週は魂葬実習だね。待ち遠しくて」
花のような二人の会話に、花太郎は一歩下がって。
同じく下がった二人組を隣に歩く。
「私たちのクラス、まだ魂葬実習したことないの」
だから初めての遠足のような気分だ、と雛森は朗らかに笑う。
「一護くんは現世に行ったことある?」
「一回だけ連れて行って貰ったことがあるよ」
婚約者にデートだと称され、連れ出されたことがある。
そう言わないけれど、一護はあの世界がとても綺麗だと思った。
穢れない美しいだけの屋敷の中よりもずっと、綺麗だと一護は思う。
「俺も楽しみ。桃さんと一緒の班になれたら良いな」
一護に出来た初めての友人。
新しい世界に踏み入れた一護は、これから花太郎の届かぬ場所へと行くのだろう。
それが誇らしくて、何処か寂しかった。
*
陰る月は時に虚をも呼ぶ、世界は酷く美しく、そして残酷だ。
「っよせ青鹿!」
一回上の、檜佐木と言ったか。
69なんて卑猥な刺青を入れた男の目前で貫かれるのは、かつて仲間であったはずの死神の卵。
既にもう一人は、虚の餌食になっている。
「くそっ」
その巨大虚は、檜佐木の目元を抉る。
血が滴り、視界を邪魔する。
殺される。
「君臨者よ!血肉の仮面・万象・羽搏き・ヒトの名を冠する者よ!」
檜佐木はそれでも刀を構えた。
「焦熱と争乱、海隔て逆巻き南へと歩を進めよ!破道の三十一、赤火砲!」
爆音、それから煙。
「お前等、逃げろって!」
言ったはずだ、と振り向き叫ぶはずだった檜佐木は、目の前で虚の爪先と刀を交わらせる青年二人を目にした。
その身が、手が震えても、刀をふるって虚の攻撃を防ごうとする。
その巨大虚を、見たこともない大きな刀が切り伏せる。
一護は、身の丈ほどの刀を振るう。
「、はぁ」
けれど息が乱れる。
たとえ刀が始解をしていようとも、場数も踏んでいない、ただの子供に過ぎない。
「っ一護!」
「黒崎くん!」
その背後に新たな虚の爪が振り下ろされようとしても、防ぐ術などない。
最も近くにいた赤髪の青年ですら。
「満たせ瓠丸」
いつも穏やかな表情で、どちらかというと自信のなさそうな少年とも青年とも取れる彼が、その爪を防がなければ。
塵と化していたはずだ。
「…大丈夫、ですか?」
「有難う…花太郎」
一護を抱き込むように、花太郎は刀を振るう。
本来攻撃に向いていない刀の威力は微々たる物でしかないけれど、その守ろうとする気概さえあれば、多少はどうにかなる。
多勢に無勢だという状況でなければ、きっと彼は一護を守りきり、その婚約者との約束を守れたはず。
「…くそっ」
四面を虚に囲まれ。
なすすべもなく、檜佐木は唇をかみしめる。
ここにいる下級生達を守らなければ、と檜佐木が決意し、振り下ろされる爪を受け止めようとした瞬間。
その爪先だけでなく、身さえも虚が立ち消える。
「藍染隊長!市丸副隊長!」
脇差しほどの刀を持つ、狐顔をしたこの副隊長とやらがあの虚を倒したのだ。
優しそうな顔つきの隊長は、頑張ったねと雛森の頭を撫でる。
それから埋め尽くすように居たはずの虚が消えるまで、さほどの時間は掛からなかった。
「大丈夫だったかい?」
藍染は改めてそう言った。
半分泣き顔の雛森は、大きく頭を縦に振った。
それから、始解を果たした刀を持つ二人組、少女、一護の方は些か顔色が悪い。
もう一人の、花太郎は、怪我を負った檜佐木の治療に勤しんでいる。
統学院生とは思えない、処置の良さだ。
それに、ああと藍染は合点がいったように。
「確かに可愛らしい子やなあ」
数多の女を袖にしてきた男が、ようやく頷いた。
いや、その身を捧げるほどに、彼は婚約者を献身的に慈しむという。
「大丈夫かい?」
「… 平気、です」
にしては、少々優れないような?
「あかんよ。気分悪いんなら、ボクが負ぶって連れて帰ったげるさかい」
一護に差し出した手が、よもや弾かれるとは思っていなかっただろう。
小さな手によって、ではない。
本当に後少しで触れようとした指先に電流が走った。
一護は驚いて、市丸を見上げる。
「…いったぁ…何なん…?」
「過保護すぎる、と言われたことがないかい?」
市丸の言葉に申し訳なさそうにして、藍染の言葉に一護は顔を上げた。
「花に群がる虫を追い払うには、このくらいしませんとねえ」
浮遊感に、うわ、と声を漏らすのは、まだ一護が幼い証だ。
子供を腕に抱き込んで、浮かぶ月の髪を持つ男は頬を寄せる。
突然現れた男を、白い羽織に十二の文字を刻む男を、目を白黒させて、花太郎以外の三人組は見ていた。
「ご無事ですか?」
「花太郎が助けてくれたし」
「それは結構」
一護は彼の胸の丈ほどもない。
浦原は一度だけ花太郎を見やって、それからぎゅうぎゅうと腕の力を込める。
「まさか大事に女性を抱く君の姿なんて、見られるとは思っていなかったよ」
伊達に過ぎない眼鏡を上げた藍染に、ふん、と浦原は鼻を鳴らす。
「近いうちにアタシの奥さんになるんですから、大切にして当然でしょう?」
これ以上目に触れさせぬ、と一護を抱いて。
尸魂界への門をくぐろうとした浦原の足を引き留めたのは他ならぬ一護だ。
今は実習中だから、と。
共に帰るのは浦原でなく、後ろで状況について行けずに狼狽える友人達だ。
「そう…残念っスね」
心底、浦原はそう言って、腕を放す。
その前に、一護の頬に唇を落として。
*
学院に戻り、怪我をした檜佐木は救護室へ。
外傷のない彼らも一応、念のためにと診察を受けた。
「浦原隊長と、婚約してるの?」
ようやく落ち着いた雛森が、その質問をするというのも自然の流れ。
「一応。たぶん」
本人が聞いたら、うざったい泣き真似が始まりそうだ。
きゃあきゃあ、と年頃の少女らしくはしゃぐ雛森に対して、当の本人は落ち着き払っている。
「婚約者だなんて憧れちゃうなあ。それも、浦原隊長と、なんて」
隊長格は皆の憧れ。
一護は微塵にも思っていないが、たぶんそうなのだろう。
鬼才と言わしめた男を、いずれ伴侶とする一護には理解できないのだ。
「でもよ。浦原隊長って、かなり年上だろ?ってことは、親が決めた許嫁、とか?」
親かどうかは分からないが、そうだ。
恋次の言葉に、一護は頷く。
「貴族ってのも大変だね」
下流とはいえ貴族出身であるはずの吉良の、そんな言葉に苦笑して。
「それが定めなんだ」
自由を許されぬのも、特権階級ゆえの。
子は親を選べぬという。
一護が王家の血筋を引く母を持ち、上流貴族の浦原に嫁ぐのもまた、運命の輪に定められていたことだ。