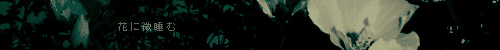
3.アイシテルは常套句
統学院を無事卒業、それも主席という華々しい成績。
入隊をあと三週間後に控えた一護は、この男と祝言を上げた。
婚約者から夫婦に。
男と同衾したのはこれが初めてというわけではない。
初夜から、いい加減飽きないかと言うほど、抱かれては幾夜を過ごす。
それでも男は、祝言を終えるまで耐えていた、というのだから。
「…っ」
身を起こした一護の、下肢に伝う白濁。
折れんばかりの細い手首に残る、青い跡。
「何処へ行かれるんです?」
腰を絡め取られる。
些か熱を孕んだ声は、少しばかり掠れる。
「一護さんはいつも、気を失ってしまわれるからご存じないでしょう?」
「…何を…?」
浦原よりも一層掠れた声で、一護は答える。
そのまま二回目を、と強請られることは少なくない。
「普通ね、睦言を囁き合うんです。愛してる、とか、可愛いね、とか」
それは散々閨で聞いたところだ。
耳にたこができるほど、聞き飽きたにも等しい。
「でも一護さん。アナタは言ってくださらないじゃ、ありませんか」
可愛いと言えば満足?
浦原が望むのは前半の言葉。
愛して、いるのか?
どのような感情をもって愛と言うのか分からないが、恋はしていた。
己の乳母子に。
生まれたときから一護に付き従う、今も一護の筆頭世話役として勤め上げる彼に、初恋は。
「アタシはこんなにもアナタを愛しているのに」
13になっても心までは大人にならぬ一護に合わせて。
ゆっくりと愛をはぐくんで、恋心を育てばよいと言ったくせして。
「おわかりにならないのなら、もう一度、繋がっておきますか?」
目尻を赤く染めた一護は、何度もかぶりを振った。
*
昼時に相応しい時刻になって。
未だに起きてくる気配のない、屋敷の主は、仕事の事なんて忘れ去ってきっと、うつつを抜かしているのだ。
「浦原様」
花太郎は。
長年使えてきた少女とその夫が居るはずの部屋の前で、声を掛ける。
幾重にも襖が重ねられる、この奥には、仲良く二人揃って寝ているのだろう。
こんな昼中まで。
「…… 失礼致します」
膝を付き、襖を一つ開ける。
その先にはまた襖が。
それをいくつか開いて、残る襖はあと一つだ。
「巳三つの刻で御座います。そろそろ、ご出勤の時刻では?」
その襖を開くことは、たとえ花太郎でも許されない。
そんな暴挙を。
なかなか出勤しないのにしびれを切らし、彼の部下、額に角のある異形の男はやってのけた。
「局長ッ!新婚なのは重々承知しておりますが、これでは研究が、」
捗りませんと続けるはずであった言葉は、男の口の中で飲み込まれた。
ひっ、と花太郎も悲鳴を上げる。
「っや、あだ…」
褥から少しはみでて、上体を伏せる少女の。
上に覆い被さる男はきっと、来訪者、強いては邪魔者の存在に気づいているはずだ。
「ひぁ…あ、ん」
くぐもったそれは、泣き声とも、啼き声とも。
卑猥な水音も手伝って、これがただのじゃれ合いではないと告げる。
立ちこめる臭いが何であるかなんて明白。
「今まで働きすぎたぐらいだ。多少仕事が滞っても構いませんでしょ?」
口を動かし、不埒な動きを止めることもない。
好き勝手、橙の髪に埋めていた顔を上げて、早く去れと言葉に出さず、告げた。
それとも見て行かれます?
くすくす笑って、枕に顔を押しつけて耐える少女の耳を犯す。
刹那、ぴしゃりという音を立てて、襖が閉じる。
例え昼中であろうとも。
お天道様が空の真上に上っても。
いくらでも寝ていられる、そんな男なのだと言うことを失念していた。
「局長の奥方、いくつなんだ?」
「え、ええ、ああ。先月13になられました」
心ここにあらず、だった花太郎は、話しかけられてようやく心を取り戻した。
先ほど目にしたことは忘れよう。
「…ロリコンだな…」
十倍は軽く年の離れた少女を、夫婦とはいえ手籠めにして。
確かに間違いではない。
現世であれば淫行罪で即刻、刑務所行き。
「…否定致しかねます…」
襖の向こうからは、小さな悲鳴と、不明瞭な囁き。
花太郎は、それにまた肩を震わせて、慣れねばならぬ、とため息をついた。