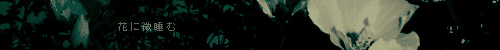
4. ココロウラハラ
春だから桜が散る。
風流だと人は褒める。
春になれば桜が咲き、そして散るのだと、つい先日まで知らなかった。
季節など関係のない箱庭に住んでいたからこそ。
「黒崎一護。そなたを十三番隊七席に命ず」
入隊式で、咲き誇った桜が散る様を見ても、一護の感慨の一つもかき立てはしなかったのだ。
頭を垂れて、一護は死神を統べる男から任官状を受け取った。
優雅ささえ感じる仕草は、その生まれが尊きものなのだと言わしめる。
「あれ。浦原はんとこやおまへんの?」
隊長羽織を纏う日も近いと囁かれる男は、隊長よりも一歩下がったところへ立っていた。
けれど前に立つ、十二の男に話しかける。
私語は厳禁。
「こればかりは、アタシが自由に出来る事じゃありません」
越権行為だと、浦原は言う。
この男からすれば容易いことだろうに、知らぬふり。
「あんさん、近頃定時に帰るって聞きましたえ?それと、無断欠勤もちらほら」
「新婚ですからねえ」
一刻でも早く、背の君の場所へ帰りたいんです。
上げるのは甘ったるい声ではなく、けれど甘ったるい視線を、その背の君とやらに向ける。
つい先ほど拝命されたばかりの少女は気づいているのだろうか。
*
箸より重いものを持たない、なんて何処ぞの令嬢か。
けれどあながち間違いではない。
身の丈ほどの刀以外、統学院生活で多少世間慣れをしたとはいえ、深窓の姫君であった一護にとって、隊務という奴は厳しい。
「良いよ花太郎。自分で出来るし」
けれど他隊に所属する乳母子に手伝って貰うほどではない。
本来四番隊七席にいるはずの花太郎は、姫君のために出張中。
「そうだ。いくら大事な姫さんだからって甘やかしたら、コイツの為になんねえよ」
と言いながら、多少は手伝ってくれているのは副隊長の海燕。
新人で七席と大抜擢の一護は、どうやら多少の肉体労働という奴を免除されている、らしい。
「だから花太郎。お前も仕事に戻って。わざわざ有難うな」
いいえ、と頭を下げて、花太郎はしずしず下がる。
上司もこの件については黙認だし、四番隊の七席とはいえ所詮お荷物部隊という認識が強くて周りも何も言ってこない。
雑用係にしか過ぎない花太郎にとって、自分のお姫様の手伝いをする方がよっぽど、生き甲斐だと言える。
「申の二つ時にお迎えに上がりますから」
「うん。ごめんな」
直々に、旦那様が迎えに来るのだろうけれど。
入隊してからすでに3週間、かっさらわれるようにして一護は浦原に連れて帰られている。
もう帰ったという連絡と毎回、ごめんという言付けを預かるのは海燕の役目だ。
「お前も大変だな」
海燕も妻帯している身、けれど新婚の時だって、これほどまでの執着を見せたことはない。
何がですか、と心底分かって居なさそうな一護を見やって、これで均衡が取れているのだと悟った。
多少薄れているものの、手首にある、手の形がくっきりと分かるような痣だとか。
人目に付くところは極力裂けているとはいえ、少し短めの髪では隠しきれない耳の後ろの痕だとか。
本来なら親の庇護の元、慈しまれるはずの子供に劣情を覚えるのは、案外容易いのかもしれない。
*
ええっと、入隊歓迎会というやつが開かれるらしくて。
それはどうやら五番隊の隊長自ら主催した、所謂飲み会。
同期の、それも同じクラスで親しかった雛森や吉良、恋次が揃いに揃って五番隊に配属されたものだから。
『一護くんもどう?』
なんて言われて、断り切れなかったと、若奥様が告げる。
「それで、オールで飲みって奴らしいけど。でもルキアも居るし」
一護が嫁入りするのと同時期に朽木家に養子入りをした、一護の十三番隊での同僚。
行っちゃだめか?と無邪気に尋ねられて、浦原もぞんざいに「ハイ」とは言えない。
構いませんよ、と懐の広い旦那様を演じてみたりして。
浦原の直々のお見送りで、歓迎会会場にたどり着いた一護は、他隊とはいえ身の狭い思いはせずに、その場にいる。
「一護の方は?お前、ちゃんと仕事出来てんのか?」
少しばかり酒の回ったらしい恋次は、呂律はしっかりしているものの、若干失礼な発言を。
「出来てる。少なくとも恋次よりは」
「何?!」
派手な見た目に対して意外に職務態度は真面目、が売りの恋次は心外だと声を荒げる。
それを宥めるのは、一護が密かに漫才コンビと名付ける相方、吉良である。
「一護ちゃん。飲まへんの?」
鬼の居ぬ間に、と。
お稲荷さまこと狐顔の市丸は、酒を片手に一護へ近寄る。
話したのは、現世で大量の虚に襲われた時、その一回ぽっきり。
「……誰?」
「市丸副隊長だよ、黒崎くん」
「ギンって呼んで構わへんよ〜」
案の定覚えていない一護は、馴れ馴れしく名前を呼ぶ男を見上げた。
ギン。
銀色の髪だからか。
「何でお酒飲まへんの?」
どうやら一護は一滴も酒を口にしていないようだ。
「下戸なん?」
下戸。
酒が飲めない人。
一護は首を振った。
飲んだことがないだけだと。
「ほしたら、これ飲んだらええんちゃう?あ、もしかして浦原はんに止められとるとか?」
その中で一番、度数が低い酒を手にした市丸に、一護はまたも首を振った。
飲んではいけないなんて、言われていない。
「じゃあ飲も。はい」
お猪口を手渡され、副隊長殿直々のお酌。
果実酒を元に作られたお酒は口当たりも良く、きっと一護でも飲めるだろう。
「……美味しい」
「そ?なら良かったわ」
一口含んで、酒の独特の苦みと、それを打ち消すほどの甘み。
一護は二口目を含んだ。
小さなお猪口をちびちびと。
「あれ、一護ちゃん?」
目尻をほんのり朱に染めた。
市丸の目に入ったのは、目をとろんと潤ませた一護の姿。
「…これは、完璧な下戸だね」
酔った素振りさえ見せない藍染は、小さく苦笑した。
確かまだ13歳だっけ?
「あかん。浦原はんに殺されてしまうやん」
え?と一護は普段より呂律の回らぬ口で受け答えする。
幼いけれどその立ちのぼるような艶やかさを色気と呼ばずして、何と名付けるのか。
「お稚児趣味なんか無いつもりやのに」
うっかり、ときめいてしまう。
庇護欲をそそるように一護のうっすら開かれた、熟れた唇に注目。
「心配に及びませんよ」
忽然と姿を現した男は、にっこりと。
護廷内で無許可の抜刀行為は禁止です。
「一護さん。せっかくのオール、ですけどお暇しましょうか」
「浦原さん?」
「何。旦那なんに名字で呼ばれてるん?不憫やなあ」
浦原を見上げて、こてりと小さい頭を傾ける一護は、浦原の霊圧が少しだけ、ほんの少しだけ上がったことに気づかない。
そのまま抱き上げられて、きょとんとした顔を向けた。
「ああ、これ。二日酔いに効く薬ですから、宜しければどうぞ?」
そう言って浦原は姿を消す数瞬前に、小瓶をいくつか畳に落とす。
中は液体。
着色料使ってます、海の色。
「……毒入りかもしれへんなあ」