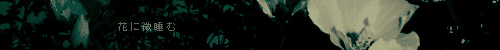
5. 甘やかな殺意
転属命令。
黒崎一護を本日付で、十二番隊五席に。
漆黒の墨で書かれた文字を見て、花太郎は内心ため息。
やると思ってた、なんて。
「昇進おめでとう御座います」
おくびにも出さず、頭を深々と。
臣下の礼を。
「こういうの、職権乱用っていうのか?」
その通り。
浦原隊長は公私混同、越権行為も甚だしく、奥方様を自分の配下にと命じましたとも。
「いえ。一護さんの実力ならば当然でございます」
問題を少しすり替える。
一護は納得いかないように、ふうんと一言。
「そういえばさ、花太郎。子供って、どうやって出来るか知ってるか?」
花太郎はついに目を白黒させた。
いつも、なさっているではありませんか。
「え…ええと?」
「早く赤さまを見たい、って言われたんだよ。と言っても、俺知らないし。まあ流石にコウノトリが運んでくるとは思っちゃいねえよ」
だがコウノトリと同じレベルだ。
そういえば箱入りの、重箱と言っても言いくらいの箱入り娘の一護には、その手の知識を極力入れないようにしていたなあ。
毎夜繰り返される行為は本来、子孫繁栄生殖行為。
たぶん男は毛頭そんなつもりはなく、ただ目の前の少女を渇望しているだけだ。
「宜しいんですよ一護さん」
突然現れたのはこの家の主。
ひょいと掬うように一護を抱き上げる。
その視界に花太郎が映ることは、未来永劫一瞬たりともあり得ない。
「今のアタシには一護さんしか要らないんですから」
それにこういう事は、本人達の都合なのだ、他人にとやかく言われる謂われなどない。
いずれ宿るはずのそこに手を当てて、うっそりと笑う。
例え自分の血を引く、愛しい娘の血肉をもって生まれてくる子供でも。
この男に興味などない。
ただ一護さえ居れば良いのだと、告げた。
*
一護ちゃんって、綺麗になったよね。
前までは可愛らしい、ってそんなイメージだったのに。
雛森は、昼休み、食堂で昼食を取りながら、そう言った。
きっと浦原隊長のおかげね、キャッ。
男ならばただの猥談になるかもしれないが、雛森は気にせずあっさりと。
ハートが付きそうなくらいテンション高く、相変わらず雛森はそういうネタが好きだ。
「桃さん、落ち着いて」
当の本人は至極落ち着き払っている。
どうやら旦那様兼上司様は、研究室に籠もっているようで今日は一緒に朝食を取らないようだ。
「ていうか、気のせいだろ」
気のせいなんかじゃありません。
と、同期の恋次と吉良+花太郎はそう思う。
綺麗になった、というよりも色気というのが。
見た目こそ変わらないかも知れないが、彼らは一護よりも長生き。
はっきり言って妹のような一護にそんなものがあるなんて、とても微妙な心境。
「良いなあ。私も結婚したい」
「桃さんは可愛いから、何度でも結婚できると思う」
「結婚は普通何度もするものじゃないよ…黒崎くん」
どういう間違った知識なのか。
箱入りのお嬢様というのは少々世間ずれをしている。
学院時代もそれで困ったことがあるのだ。
「ふうん…」
「違う奴と結婚したいとか思ってんのか?」
少し不満そうな一護に、恋次は浦原がいれば殺されるかも知れない言葉を吐いた。
吉良と花太郎、持病は胃炎です、組は慌てて辺りを伺う。
良かった、誰も聞いていないようだ。
「別に、浦原さんが嫌なわけじゃないけど、あの人、性格悪いし」
ごもっとも。
一護に向ける優しさなんて微塵も持ち合わせない、その矛先にいる花太郎は頷いた。
「大体、俺、十三番隊気に入ってたのに、移動とかありえねえと思ったよ」
「そ、そうか…」
倦怠期か?
と思ったが恋次は口にしない。後が何となく怖そうだ。
「変態だし、鬼畜だしサドだし」
一護は護廷に入って、いや十三番隊に入って語彙が増えたな、と花太郎は遠い目をした。
良家の子女がそんな言葉を。
きっとルキアあたりの影響だ。彼女も養子とて朽木家の一員なのに。
「やったら浦原はんと別れてボクと結婚せえへん?」
にゅ、っと。
気配を消して吉良の後ろから登場した男の手には、Aランチ。
吉良は総毛立った。
「いや…アンタも変わらなそうだし…」
吉良はその時、ああもう、この場にいる人間は皆殺しかも?!なんて思った。
一護はおべんちゃらを使うような人間ではないところが好ましいのだが、困る。
「…残念やわ…」
死を覚悟した一行(一護以外)だったが、大して市丸に気分を害した様子はない。
本気なのか建前なのか、そう呟くと彼は余っていた席に座った。
「まあ浦原はんが変態なんは分かってたけどなあ」
この際彼の変態っぷりを洗いざらい、暴露してやろうと口を開いた市丸の首に一つの刀。
しかも始解済みだ。
「そんなにいやなん? 自分の悪行言われるんは」
「悪行だなんて失礼ですねえ。諸悪の根元に言われたくないですよ」
籠もってるんじゃなかったのか?という疑問を浮かべた目で、一護は浦原を見上げたが。
「ま、アタシはどうせ変態の鬼畜でサドですし?このまま紅姫でかっ斬って差し上げても宜しいんですけど」
聞いていらっしゃったんですね。
流石の一護の顔も真っ青だ。
「骨くらいはそうですね、そこにいる部下達が拾ってくれるんじゃないですかねえ?」
「いややわ。あんさんの冗談は面白ないなあ」
「冗談ではないんですけどねえ」
そう言いながら、浦原は紅姫を鞘に収めた。
にこにこと口元は笑みを浮かべて、けれど目が笑っていない。
一護の背中にひんやりと冷たい汗が流れる。
「一護さん。あとで、アタシの研究室にいらっしゃいな」
そう言って、浦原は去った。
不機嫌のくせにやけに楽しそうなのは、きっとこれからのことを思って、だ。
その頂いた称号の通り、彼はきっと変態で鬼畜でサドなことをするに違いない。
「……早引きしたい…」
一護は心底そう思ったが、残念ながら上司は変態鬼畜サドの浦原様だ。
職権乱用。
山本総隊長に訴えればどうにかしてくれるだろうか。
冷や汗どころか脂汗まで流し始めた一護に、その場にいた人々は心の中で合掌した。